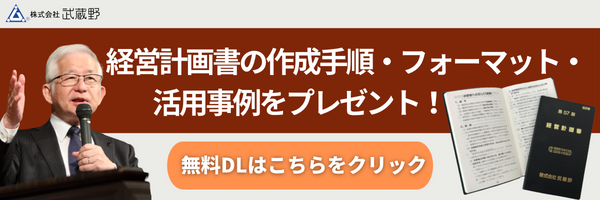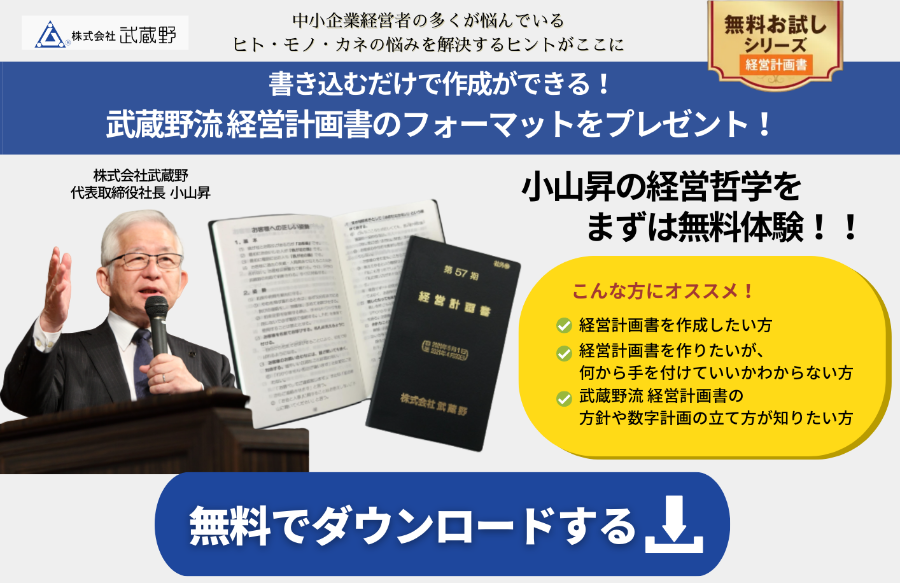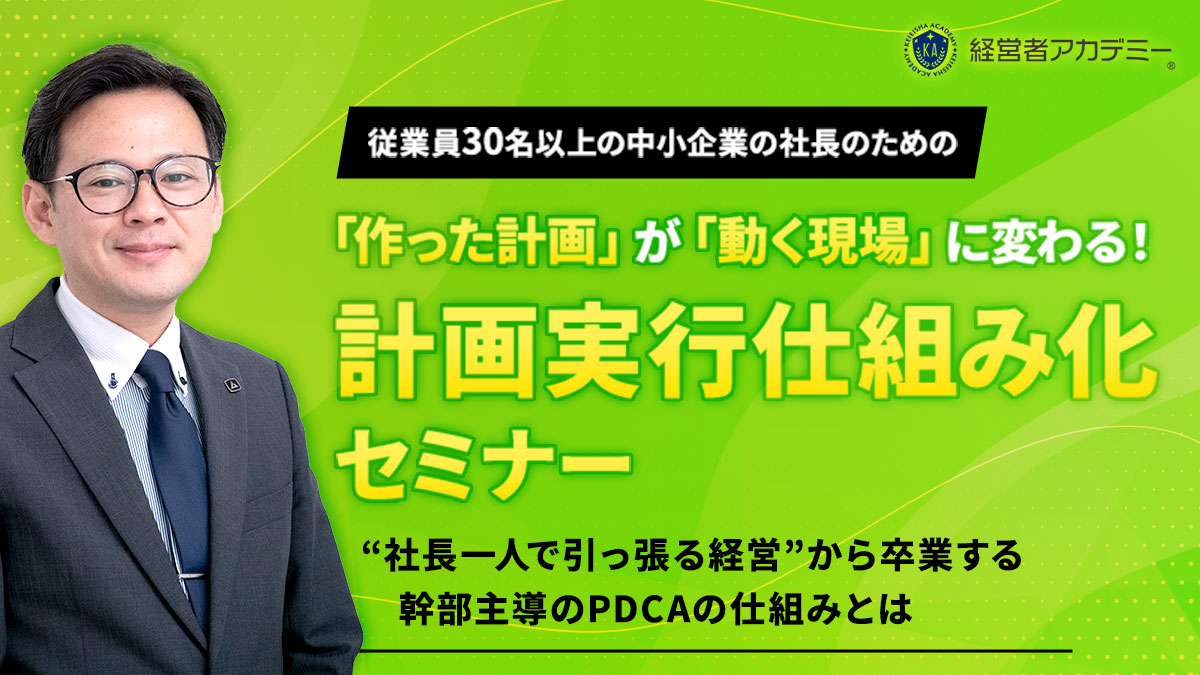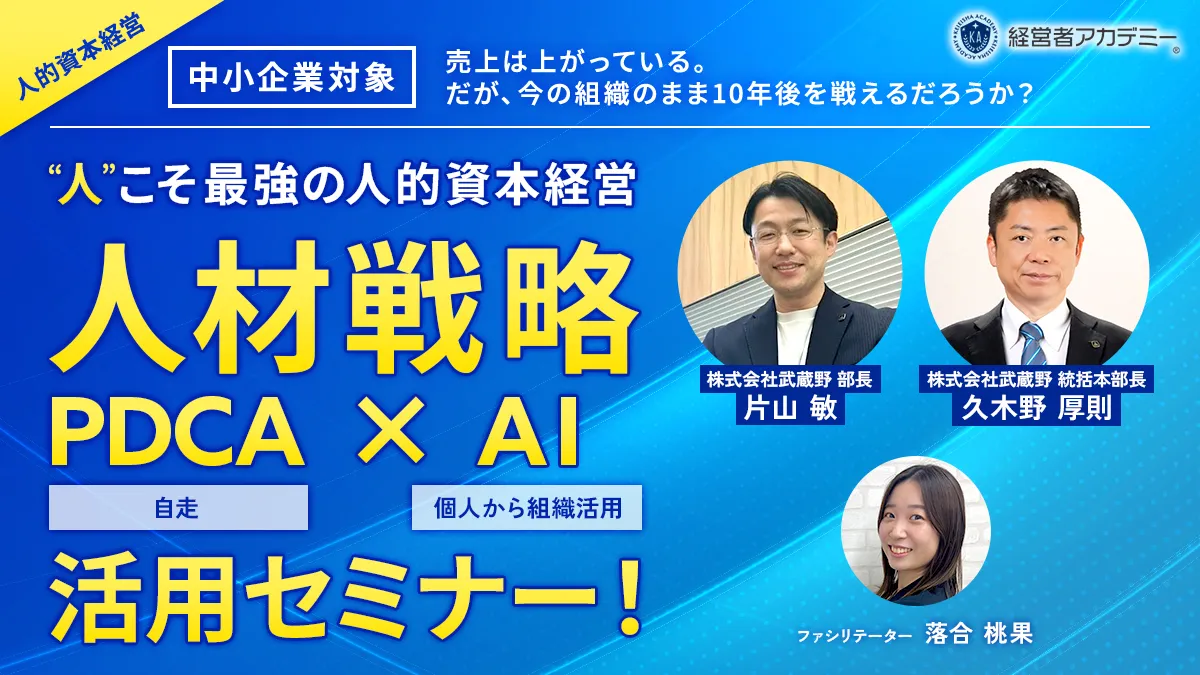いくら指示を出しても言うことを聞かない社員には困ってしまいがちです。
全く動かないわけではなくとも、方針やルールに従って動かない、うまくいかない方法でしか仕事をしないといった人もいます。
この記事では、指示出しが下手な方の特徴や、人を動かすために心しておきたいポイントについて解説します。
指示出しが下手な方の特徴
部下のスキルが高いのにも関わらず、部下の業務が進まない場合は、上司の指示出しに問題があるかもしれません。
指示出しが下手な方の特徴を紹介します。
指示の内容が抽象的
指示の内容が抽象的だと、部下はどのように進めればいいかイメージがしにくく、業務が滞ったり、仕事のミスが増えたりします。
やることだけを伝えるのではなく、指示をした内容の理由を伝えて、それを聞いてから指示の対応をすると、失敗が少なくなりますし、部下の仕事能力が上がりやすくなります。
一度にたくさんの指示を出す
一度にたくさんの指示を出すことも、指示出しが下手な方の特徴の1つです。
そもそも人間の脳の容量的に、一度にたくさんの指示を出しても記憶できません。部下は対応できなくなり、その結果業務がストップしてしまうので気をつけましょう。
指示の出しっぱなし、期限を言わない
例えば、部下に「すぐやれ」と指示を出すことは多いと思います。しかし、「すぐ」とはいつなのか、上司と部下の間で意見が異なり、上司は、本当に今すぐにやってほしい内容だったとしても、部下は今日の夜までと勘違いして、トラブルになる場合もあります。
適度なタイミングで部下の進捗を確認することは、遅延や失敗を防ぐだけでなく、部下のスキルを把握するうえでも役立ちます。
人を動かすために心しておきたいポイント
人を動かすための上手な指示だしや心しておきたいポイントを3つ解説します。
具体的な指示を出す

具体的な指示を出すように心がけ、必要に応じて内容を口承で確認して確かに指示を理解したと納得できるようにするのが大切です。指示をするときには「誰が」「何を」「いつ(までに)」「どのようにして行うのか」という4つの観点を必ず伝えるようにしましょう。
「この会議資料の校正を明日の10時までに仕上げておいて下さい。英語の誤りをきっちり直して欲しいから君にやってもらえると助かる」という指示の仕方をすれば誤解されることはありません。
同じような会議で使われた資料があれば、サンプルとして一緒に渡すとどのくらいのレベルで校正をすれば良いかもわかり、仕事に取り組みやすくなります。
このように具体的な指示を出すことで人を思い通りに動かすことができるようになります。
今まで一度も出したことがない指示をするときや、類似の指示を出したことがあるときには、できるだけ具体的で詳しい内容を説明するのが肝心です。
相手の経験やスキルを考慮する
良い指示出しをする為には、相手の経験やスキルを考慮することです。指示(業務)の達成可能性まで考えて、無理難題を押しつけないようにすることが的確な指示出しへとつながります。
ただ、考慮するあまり簡単な指示ばかり出していると、部下の成長につながらないだけでなく、「仕事ができないと思われている」と勘違いされて関係性が悪化する恐れもあります。
部下の経験値によって期限を調整したり、育成も兼ねて少しレベルの高い業務を任せてみたりと、相手によって指示の内容を変えていきましょう。
自分の言葉で気づかせる

周りの声を聞いて修正できる人であればだんだんと成長して自発的に正しい行動を起こせるようになるというのはわかっていても、聞く耳を持たない人だからどうしようもないと、あきらめてしまうかもしれません。
このようなときに重要なのは、言っても無駄だというのを受け止めた上で、自分で気づかせるようにすることです。
具体的には問題の社員に対して質問をして何をすべきかに自分で気づかせるのが効果的です。
「この問題を解決するにはどうしたら良いだろうか」と問いかけることから始めても良いでしょう。
「こうなれば問題が解決する可能性がある」と思うという答えが返ってきたら、「ではそうなるには何をしたら良いだろうか」という形で質問を繰り返していき、具体的なアクションを自分自身で考えさせるのが良い方法です。
オープンクエスチョンにすることで行動の内容が自分で考えたものになり、他人から指示されたものではなくなります。
うまく意図しているアクションに気づくように誘導するのが大変ですが、上手に話を運ぶことができれば高いモチベーションを持って取り組んでくれるでしょう。
指示出しで注意すること
最後に指示を出す際に注意する点も意識しましょう。
命令口調にならない
いくら上司でも上から目線で物事を伝えるのは避けましょう。命令口調で指示を出すと、部下が委縮してしまい、仕事のパフォーマンスが落ちます。
さらに上司へ対する信頼度も下がり、部下がついてこなくなります。チームとしての成果を挙げづらい状態になるため、命令口調で話さないように心がけましょう。
誰でも良いという形で指示出ししない
仕事のやる気を出してもらうには、自分事として話を聴いてもらうことが効果的です。
例えば「スキルが備わっているから任せた」「〇〇さんはこの分野が得意だから指示を出した」といった形でポジティブに伝えると、部下は上司に信頼してもらったと感じます。結果、仕事に対するモチベーションアップにつながるでしょう。
原因を考えて人を動かせるようになろう

思い通りに人を動かすのが難しいと思っている人は原因を考えて対策を立てましょう。
言うことを聞かない社員には質問を通してやるべきことに自分で気づくように誘導するのが効果的です。指示通りに仕事をしてくれないときにはもっと具体性のある指示を出しましょう。
このような工夫を通してリソースの有効活用を図っていくのが大切です。
株式会社武蔵野では、「経営計画書」を毎年作成しております。
経営計画書とは、会社の数字・方針・スケジュールをまとめた手帳型のルールブックです。
経営計画書があるので、目標のために何を実行しなければいけないのか、従業員全員が足並みを揃えやすくなります。
また従業員は経営計画書を見れば、会社のことがすべて分かるようになっているため、迷わず主体的に業務に取り組めるようになります。
成功企業の経営に欠かせない「経営計画書」フォーマットを無料でプレゼントしていますので、ぜひこちらからダウンロードしてください。



 ポストする
ポストする シェアする
シェアする LINE
LINE この記事は約4分で読めます。
この記事は約4分で読めます。