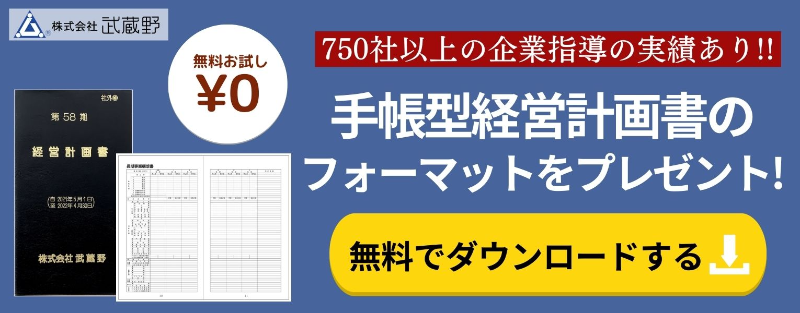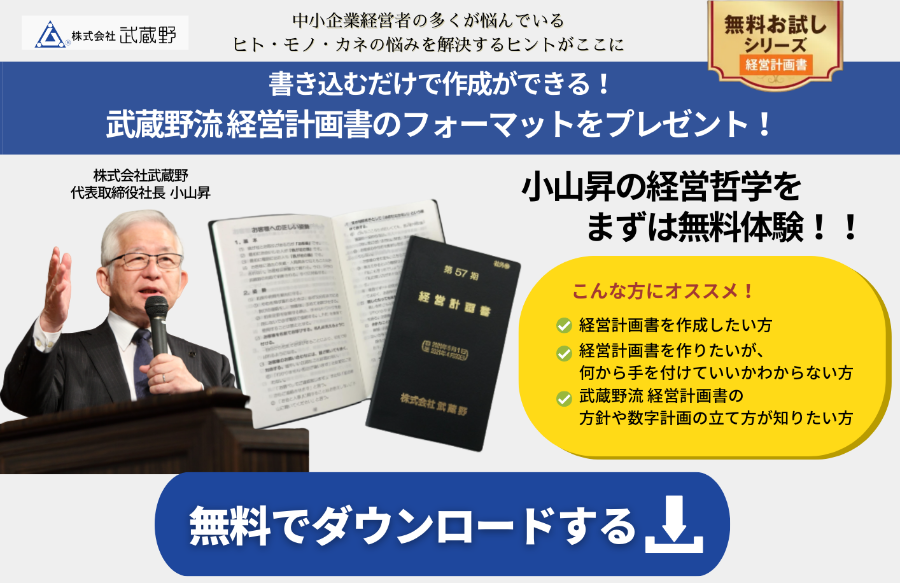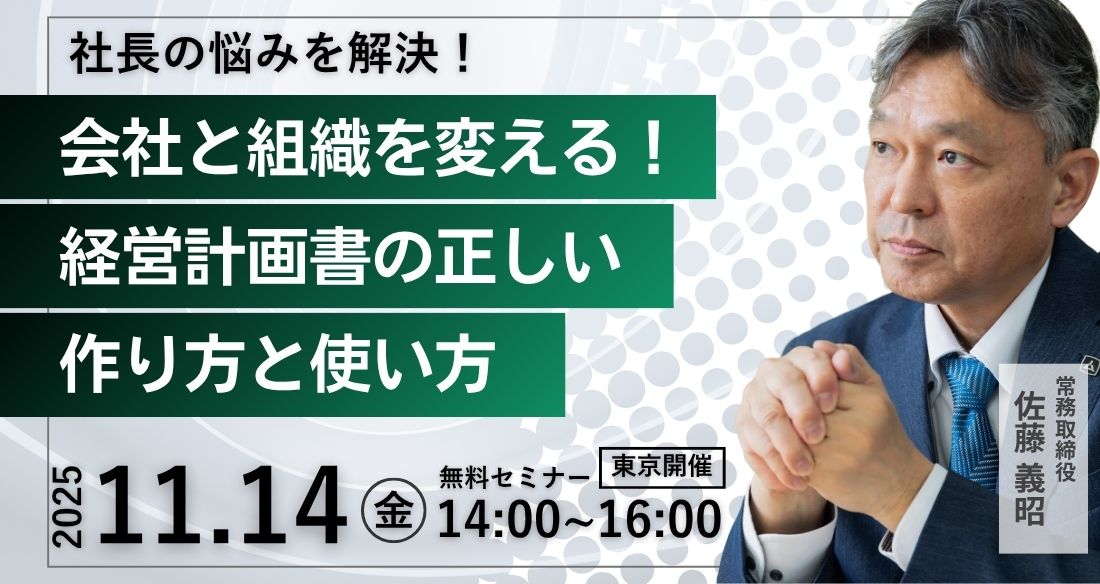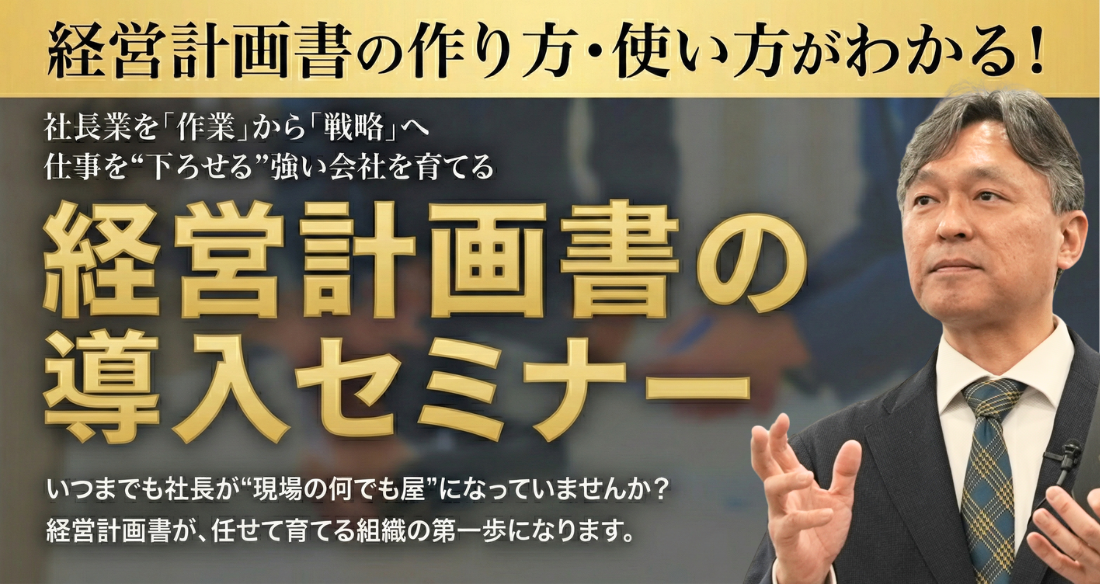健康経営とは、経営課題の一つに「働いている人の健康管理」を入れる経営手法です。アメリカの臨床心理学者によって提唱された「ヘルシーカンパニー」に基づいています。
今までは、健康管理と経営管理は別のものとして行われていました。しかし、従業員の健康増進こそが企業経営を助けるという考えに基づき、健康管理と経営管理を統合するようになったのです。
また、健康増進や管理にかかるコストは、将来への投資として捉え、前向きに資金投入する企業も増えています。
さらに、人生100年時代とも言われ、経営者だけでなく従業員の高齢化も進んでいるでしょう。高齢従業員の健康にも気を配り、知識やスキルを若い世代へ伝承していくことも必要です。
本記事では、健康経営の進め方や導入する際の注意点、事例などをご紹介していきます。
健康経営の背景と目的とは?

健康経営が注目された背景には「労働人口の減少」と「長時間労働に対する考え方」があります。日本では少子高齢化社会によって、労働者不足が問題です。よって、1人1人の生産性を向上させないと、企業の生産性も低くなってしまいます。
また、労働人口の減少で従業員の仕事量が増えた場合、残業をすることが多いです。ただし、長時間労働の増加やストレスの多い企業は、従業員の身体的負担も大きくなります。
身体的負担を少しでも減らすためには、体調の不具合だけでなく、心理的な問題も解決しなければなりません。健康診断やカウンセリングによる心身的な管理をしていくことで、従業員が健康的かつ意欲的に働けるのです。
健康経営の目的やメリットは、「労働生産性の向上」「企業価値の向上」「健康経営優良法人への認定」「助成金が受けられる」です。
労働生産性の向上
従業員が心も体も健康だと、仕事への意欲が上がります。業務をするスピードも上がるとされ、労働生産性が向上するでしょう。積極的に意見を出したり、情報収集したりできれば、業務の質も高くなります。従業員の生産性が全体的に上がれば、企業の業績も上がるのです。
企業価値の向上
健康経営ができている企業は、従業員が働きやすい職場として評価されます。高い評価を得ていると、企業価値の向上にも繋がるでしょう。
例えば、従業員の離職率が大きく関係しています。離職率は、新卒者や転職希望者が応募する企業を選択する時の判断材料です。働きやすい企業として企業価値が上がれば、意欲のある学生や転職希望者が応募してきて、優秀な人材が集まりやすくなります。そして、いい人材が集まれば、企業の業績や価値もさらに上がっていくのです。
企業価値は取引先や投資家からの評価とも関係しているため、企業の資金集めや収益にも繋がります。
健康経営優良法人への認定
政府は「健康経営優良法人」の認定制度を実施し、健康経営の推進をしています。健康経営を実践できている企業が、経済産業省から認定される制度です。認定基準は「経営理念」「組織体制」「制度や施策の実行」「評価と改善」「法令遵守・リスクマネジメント」の5項目があります。そして、認定されると、健康経営優良法人のロゴマークが使えるようになるのです。会社のホームページや従業員の名刺などにロゴマークを入れて、健康経営ができている企業としてアピールできます。
また、金融機関からの低金利融資や自治体からの資金調達など、さまざまな優遇措置が受けられる可能性もあるでしょう。
助成金が受けられる
健康経営に関する取り組みをしている企業には、助成金が支給されています。「時間外労働等改善助成金」は、時間外労働の上限を設定している中小企業を対象にしたものです。労働時間の短縮を図りながら、労働性を向上しようとする事業主に一部の費用を助成しています。
「業務改善助成金」は、最低賃金の金額を上げた場合や設備・サービスを導入する企業に対して、費用の一部を助成するものです。その他にも、「職場定着支援助成金」「受動喫煙防止対策助成金」などがあります。
健康経営はどのような企業が取り組むといい?
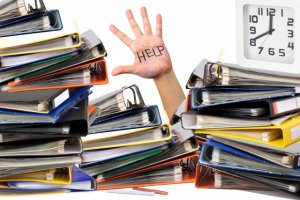
健康経営に取り組んだ方がいい企業は、従業員のストレスチェックで悪い結果が出てしまったところです。2015年からストレスチェックが義務化されていて、その結果によっては対策が必要です。役職別や年代別・部署別に結果を分析し、健康経営に関する課題を明確にできるといいでしょう。
また、長期休業者が増えている企業も、健康経営を取り組むのが望ましいです。長期休業者は体の病気だけでなく、ストレスや不安などからくる心理的な要因もあります。健康診断やカウンセリングを気軽に受けられる環境が整っていると、長期休暇を選択する前に解決できる可能性もあるのです。そして、従業員の企業に対する満足度も上がりやすくなります。
人材不足や労働時間が長い企業も、健康経営に取り組むことが必要です。人材不足によって、従業員1人1人の負担が大きくなっていると、全員が不調になる可能性もあります。労働時間が長いと、不調があっても健康診断や病院に行く時間がなく、放置してしまう人もいるでしょう。
従業員の健康管理ができないと、企業全体の業績も落ちてしまいます。また、企業によっては、従業員の多くが中高年です。そのような企業も、積極的に健康経営を取り組むといいでしょう。若い世代の死因は自殺や不慮の事故ですが、中高年の死因は悪性新生物や脳血管疾患・心疾患などです。定期的に健康診断が受けられると、病気の早期発見と治療ができます。
健康経営の進め方とは?

健康経営を始める時には、最初に「健康経営を行う告知」を社内と社外に伝えます。企業の考え方を従業員や投資家・取引先などに知ってもらうことが大切です。
その後、経営理念に基づいた指針を考えていきます。その際、加入している健康保険協会や組合によっては、「健康宣言事業所」を募集しているため、事前の確認が必要です。
宣言後は「組織の体制作り」を強化します。例えば、専門部署を立ち上げ、健康管理を進める体制を作っていくのです。知識が少ない場合は、研修や専門的なアドバイザーを雇うなどの対策も行います。
体制が整った後は、「課題の確認」を行います。まずは、従業員の体調把握やストレスチェック・健康診断の頻度などを調査していくと、課題が明確になっていくでしょう。
また、従業員から働き方や健康面に関する聞き取りをすることも大切です。課題の具体例として、「残業が多い」「特定部署でストレスを感じている人が多い」「健康診断受診率が低い部署がある」などが挙がってきます。残業だけでなく、休日出勤の頻度や時間・有給の消化率も確認するといいでしょう。
課題が明確になった後は「計画の作成と実行」です。取り組む課題の解決方法を考え、従業員が実践しやすい計画を作成します。例えば、「全員が残業しない日を設定」「食事や運動指導を受ける」「健康に関するセミナー開催」「業務中でも身体を動かせる環境を作る」などです。
実行後は、課題と対策に対するフィードバックを行い、「継続して実行できるか」「もっといい方法はないか」などを考えていきます。
健康経営を導入する際の注意点は?
健康経営を導入する際の注意点を3つ解説します。
従業員の負担が増える場合がある
健康経営を導入することで、従業員が取り組む課題が増える可能性があり、課題が増えることでストレスを感じる人もいるかもしれません。従業員の負担が増え、ストレスを増加させてしまっては本末転倒です。経営計画を周知させ、従業員が受けるメリットを浸透させることが大切です。
効果を把握しにくい
健康経営は長期的な取り組みとなるため、健康経営の効果が現れるまでには、ある程度の時間が必要となります。また、全社的に取り組む課題ですので、個人では効果を感じにくい点もあります。短期的な業績で判断するのではなく、長期的な視野で、従業員の労働時間、業績、ストレスチェックなどの総合的なデータから効果を分析することが重要です。
データ管理のコストがかかる
健康経営の実践には、まず従業員一人ひとりの健康状態を把握するデータを収集して管理するためのシステムが必要となります。
システムの導入には、コストが発生し、また適切に運用するには、そのための教育や人材も必要となります。しかし、長期的な視点にたてば、健康経営を実践する方が企業にとってメリットが大きいと考えられます。
健康経営では女性社員への配慮も重要!
SDGsでも、ジェンダー平等や女性のエンパワーメントが現代社会における重要なテーマになっています。健康経営においても、企業は女性のライフステージに合わせたサポート体制を用意する必要があります。
例えば出産手当や不妊治療の支援、復帰後の適切な部署配置などが求められます。女性の健康を保持し、女性が働きやすい環境を構築していきましょう。
また近年では、女性だけでなく、男性も育児休暇が取りやすい環境が増えてきました。制度によっては、赤ちゃんが1歳2か月を迎えるまで育児休暇が取得できる企業もあります。
健康経営の企業事例を紹介!
実際に健康経営を実践している企業3社の事例を紹介いたします。
イオンモール株式会社
全国にショッピングセンターを展開するイオンモール株式会社では、グループ一体となって従業員の労働安全衛生と健康経営に取り組んでいます。
2016年と比べて2021年の定期健康診断受診率0.9%アップ、ストレスチェック受検率44.9%アップ、法定外労働時間発生割合0.438ポイントダウンを達成するなど、着実に成果が上がっています。
新関西製鐵株式会社
平鋼という鋼材を製造・販売している新関西製鐵株式会社では、メンタルヘルスの不調の早期発見や職場復帰支援を目的にした「リワークプログラム」を実施しています。プログラムに参加した従業員全員が職場復帰に成功しており、プログラムの目的と目標を達成しています。
株式会社タニタヘルスリンク
体重計など計測器の大手メーカーである株式会社タニタのグループ会社、株式会社タニタヘルスリンクでは、従業員が自ら健康経営のPDCAサイクルを回すことができるようにしています。
重点施策として、メタボリックシンドロームの解消による生活習慣病や疾病のリスク軽減を掲げ、2021年時点で適正体重維持者が74%を超えました。
健康経営について知り、導入してみよう!

健康経営を導入することで、従業員の健康増進を図るだけでなく、業務の生産性や業績の向上にも繋がります。また、従業員の満足度が高くなり、仕事へのモチベーションも高まるでしょう。
健康経営を始める場合、政府からの認定制度や助成金制度も活用できます。健康経営を実施し、従業員が大切であることを伝えるのは、経営者にとって大切なことです。これを参考に、健康経営について理解し、導入してみてください。
株式会社武蔵野では、「経営計画書」の無料お試し資料をプレゼントしています。経営計画書とは、会社の数字・方針・スケジュールをまとめた手帳型のルールブックです。
750社以上の企業を指導する株式会社武蔵野 代表取締役社長 小山昇の経営哲学が詰まった
経営計画書の作成手順・作成フォーマットがセットになった充実の内容となっています!
ぜひ、こちらからダウンロードしてください。



 ポストする
ポストする シェアする
シェアする LINE
LINE この記事は約3分で読めます。
この記事は約3分で読めます。