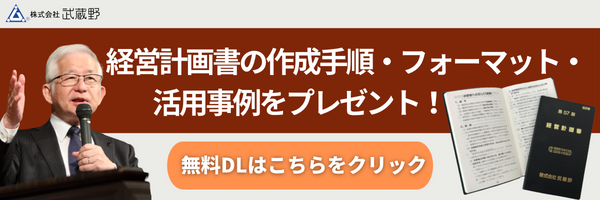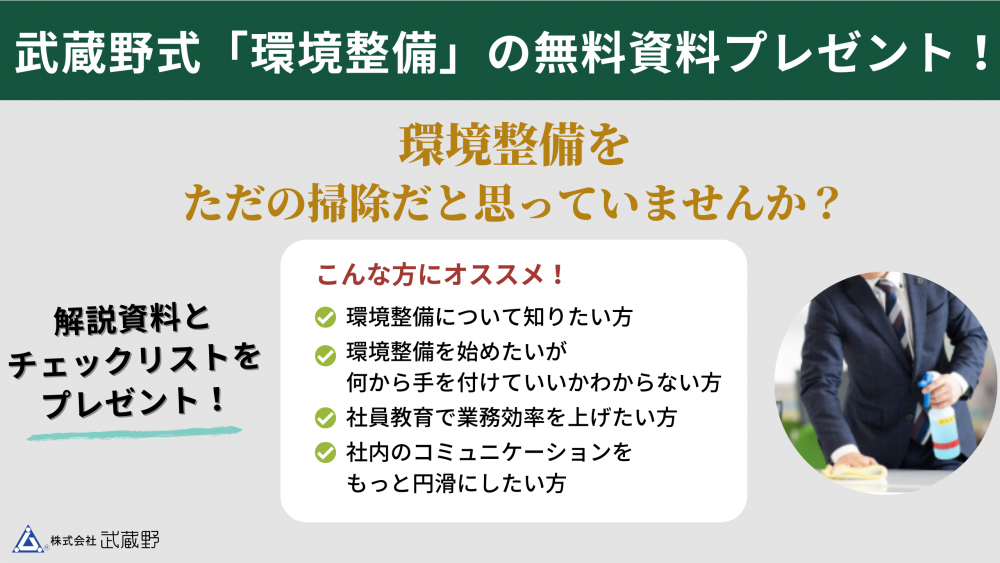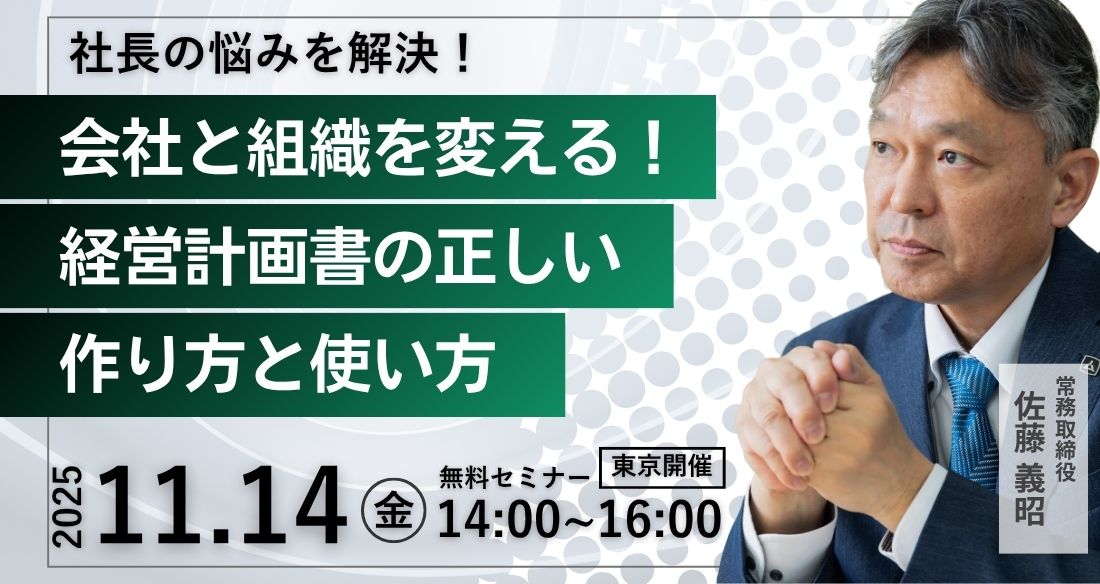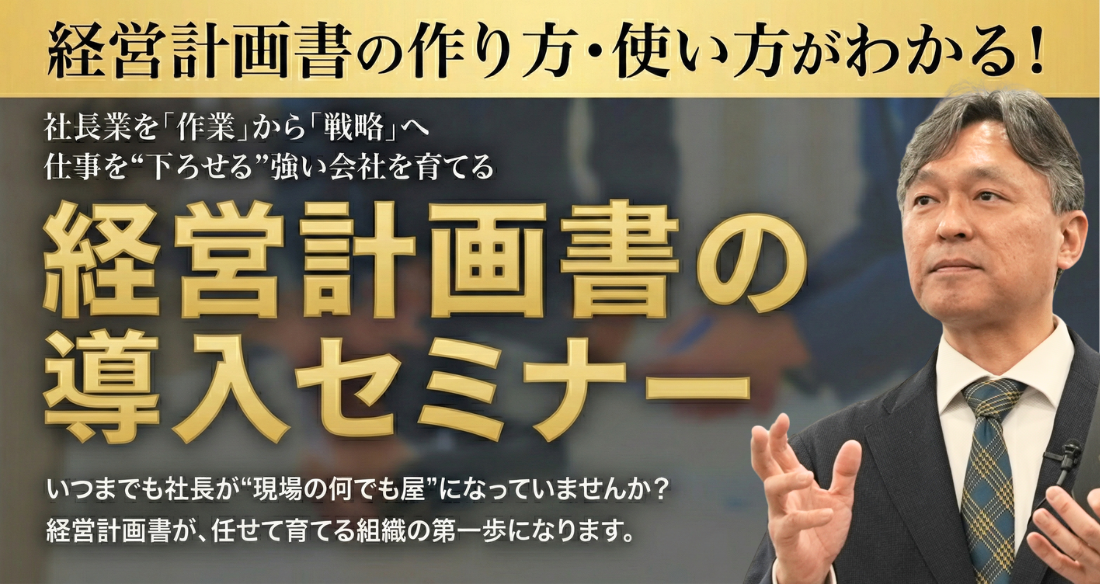休憩時間は、労働者にとって心身を健やかに保つために必要な時間として労働基準法で定められており、雇用形態に関係なく適用されます。
こちらの記事では、休憩時間の基本ルールや、適切な休憩の仕方について紹介します。
労働基準法が定める休憩時間
労働基準法では、次のように労働時間に応じて取得すべき休憩時間を定めています。
「使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。」
また基本ルールとして、「休憩時間の3原則」が労働基準法で定められています。時間的には適切に休憩が取れていても、3原則に則っていない場合、適切な休憩時間が与えられていないと判断される可能性があるため注意が必要です。
途中付与の原則
途中付与の原則とは、「休憩は労働時間の途中に与えなければならない」というものです。就業前や就業後に休憩を与えることは法律違反とみなされます。
また、休憩時間を分割させても途中付与の原則には違反しないですが、小刻みな休憩時間は疲れを癒す観点では効果が低いため不十分と判断される恐れもあります。そのため、まとまった休憩時間を労働途中で付与するのが適切です。
一斉付与の原則
「休憩時間は一斉に与えなければならない」という原則のことを指します。一般的に「昼休み」がこの原則に該当します。
ただし以下の業種については、その特性から労働者が一斉に休憩をとることが困難として、「一斉付与の原則」の適用外とされます。
・運輸交通業
・商業
・金融業
・興業
・通信業
・保健衛生業
・接客娯楽業
・官公署事業
※労働基準法40条および労働基準法施行規則第31・32条
また、業務形態によって一斉付与が難しい場合も、労使協定を締結することで一斉付与の適用外とすることが可能です。
自由利用の原則
労働基準法には「使用者は、第一項の休憩時間を自由に利用させなければならない。」と記載があります。
つまり、休憩時間を従業員がどのように過ごすかを企業側が干渉することを禁じています。休憩時間中に業務を依頼する行為などは、法律違反となります。
ただし、警察官や消防員など、一部職種・業種によっては自由利用の原則の例外となることが規定されています。
休憩時間をデザインする方法
休憩時間の間は、脳と体をリフレッシュさせることが大事です。
例えば仕事の一日がパソコンでの作業が多い場合、休憩時間にSNSやネットサーフィンは活動内容が変わらないので脳が休めていません。
なので新鮮な空気を得るために散歩する場所があれば、数歩歩いたり、肩や首をリラックスさせたりして、何よりもパソコンから視線をそらすことをおススメします。
あるいは、胸式呼吸と腹式呼吸などの呼吸法で代用もできます。現代人は上半身の筋肉を動かし「息を吸う」ことを得意としています。これは「ヤル気を出すぞ!」という緊張状態にある時の呼吸です。
気持ちを安定状態にするためには、意識して「息を吐く」ことをしましょう。特に午後の憂鬱な時間の前にしっかりと呼吸運動を繰り返すことで効果が期待できます。
また、十分に飲み物を飲むことも大切です。水分不足でも集中力やパフォーマンスの低下につながります。
適切な休憩と気晴らしとの違いですが、気晴らしにはネットサーフィン、ソーシャルメディアチャネルのスクロール、テレビの視聴、コンピュータゲームのプレイなどが含まれます。
これらの活動は何万もの刺激で心を溢れさせます。したがって、これらの活動をしている間は、刺激に溢れ休むことができていません。
読書、音楽鑑賞、オーディオブックは同じではありません。運動、ガーデニング、社交、瞑想は再生とリラクゼーションにつながります。安らかな睡眠も非常に重要です。
小休憩で生産性と集中力を維持するには
研究では、1分未満の小休憩でも、1日を通して生産性と集中力を維持するのに十分であることが示されています。定期的に短い休憩を取るようにしましょう。
原則として、90分集中して作業した後は、2~5分程度の休憩を取るようにしましょう。
例えばコピーをとりに行ったり、トイレに行くときは、業務の目的のためにいくつかの深呼吸をします。または、一瞬目を閉じて呼吸に集中してみましょう。どちらも体を休ませてくれるので、時間がかからずに済みます。
そして、「昼食後の眠気」に深く陥らないように、お昼過ぎに3分から5分程度のミニ休憩を計画しましょう。
重要なのは、この休憩時間を本当に計画し、理想的にはリマインダーを設定することです。
また、体が疲れのサインを送ってくるときにも注意しましょう。体が休憩を欲する時は個別に休憩時間を設定するようにしましょう。
このような兆候が見られる時は集中力の欠如、ミスをしやすくなる、筋肉が緊張して目が重くなるなどが表れます。
まとめ
休憩は人によって異なります。パソコンと接するのであればパソコンから離れ、肉体労働や営業活動などで体を動かすのであれば体を休ませます。
全ての人から時間に対する不公平感を取り除き、主業務とは異なるプラットフォームで休憩をデザインし、実施する事が重要です。
労働基準法で定めている休憩時間を守り、自分に合ったリフレッシュ方法を行うことでよりパフォーマンスをあげていきましょう。
株式会社武蔵野では、「環境整備」を毎朝30分全従業員が行っています。
ただ掃除をするだけでなく、業務の見える化や改善、習慣化まで整える仕組みとなっています。
就業時間内に行うので体を動かしながら、また他のメンバーとコミュニケーションを取りながら行うので気分転換にもなります。
ぜひ武蔵野流環境整備を取り入れてみませんか?
自社の環境整備レベルがわかるチェックリストと資料を無料でプレゼントしています。
ぜひ、こちらからダウンロードしてください。
無料お試し資料&環境整備チェックリスト[icon name=”up-right-from-square” prefix=”fas”]



 ポストする
ポストする シェアする
シェアする LINE
LINE この記事は約4分で読めます。
この記事は約4分で読めます。