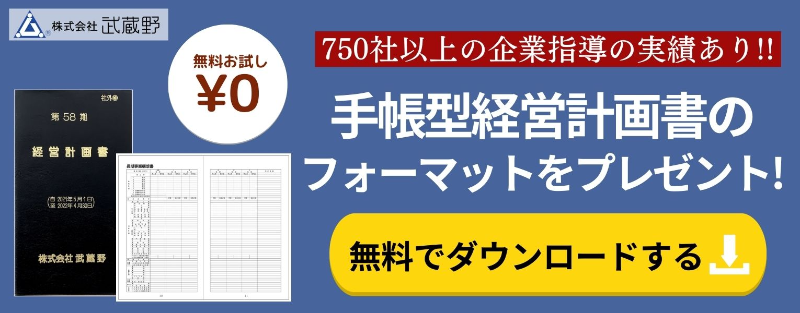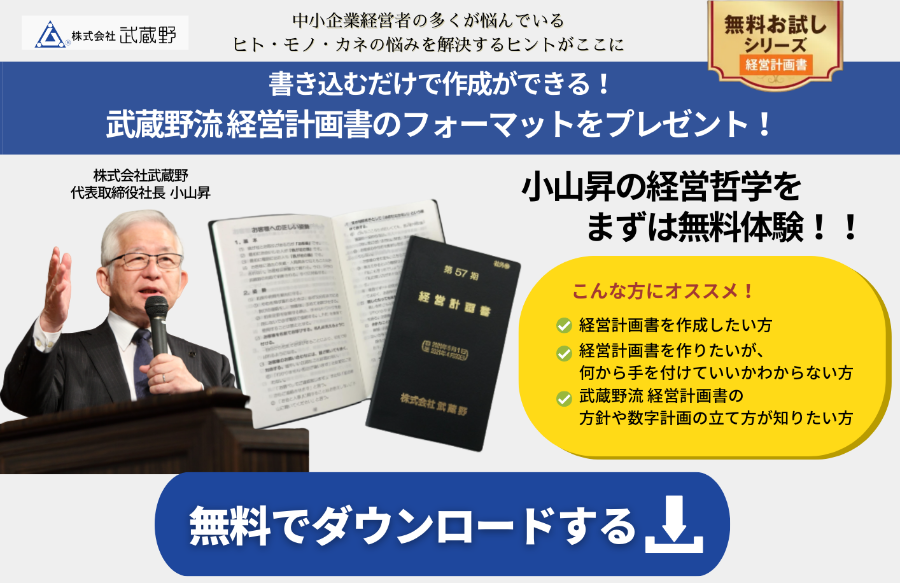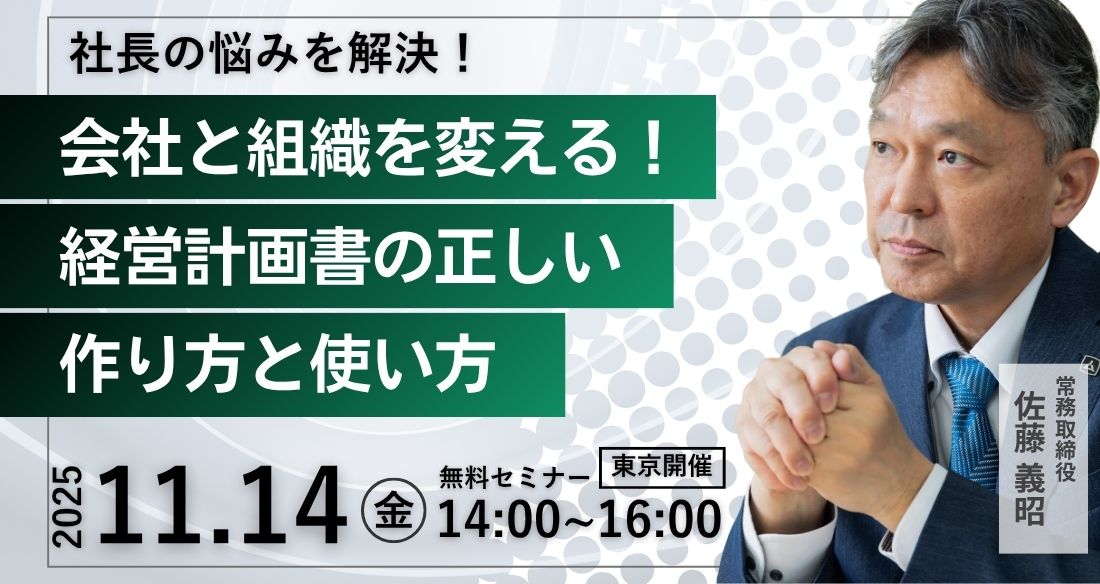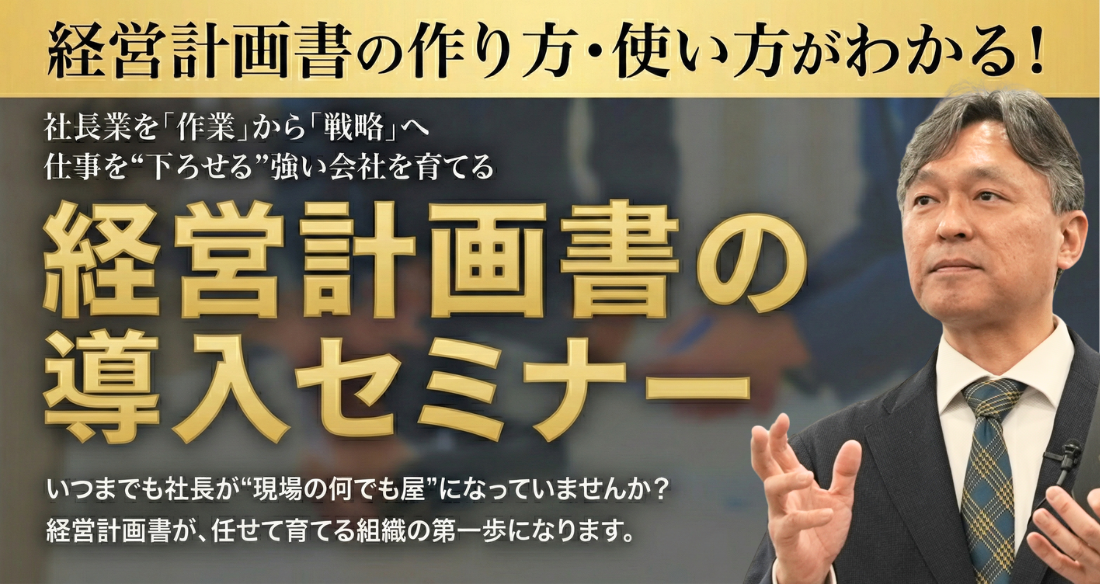ESGとは、「環境(Environment)」「社会(Social)」「企業統治(Governance)」の頭文字をとった言葉です。
環境問題や社会貢献について考える時に利用されています。
日本の企業でも、ESGを取り入れた企業経営戦略として、それに関する「統合報告書」を発行するところが増えています。
本記事では、ESG経営の特徴や課題、事例をもとに解説していきます。
ESGの意味と考え方とは?

ESGとは、「環境(Environment)」「社会(Social)」「企業統治(Governance)」の頭文字をとった言葉です。
環境問題や社会貢献について考える時に利用されています。
環境省が2015年にESG検討会を設置し、日本におけるESGの動向を入れた「ESG解説書」を発表しました。
ESG解説書は、ESGの意義や課題・取り組みの方向性などが記載されています。
ESGを取り入れた経営は「ESG経営」と呼ばれています。
企業が長期的および持続的に成長するためには、ESGの価値を追求すべきと考えていることが特徴です。
短期的な利益や成果だけでなく、長期的な企業価値の向上を目標にしています。
ESG解説書でESGについて理解する人が増え、ESGを重要視する消費者や投資家が増えています。
よって、ESG経営を実践している方は、ブランドの価値や収益にも反映されやすいでしょう。
日本の企業でも、ESGを取り入れた企業経営戦略として、それに関する「統合報告書」を発行するところが増えているのです。
ESGの経営戦略は、国連が発表している「持続可能な開発目標(SDGs)」を参考にしています。
気候や貧富格差・教育・消費などを考慮し、全ての人が平和に暮らしていくための開発目標です。そして、ESGに関することも課題や提案がされています。
以下にESGの具体的な内容をご説明します。
環境保全に対する取り組み(Environment)
企業の活動が環境にどのくらいの影響を与えるかを考えることです。ネガティブな影響が出る時には、なるべく減らす方法や改善策を出します。
例えば、省エネやスマートエネルギー・温室効果ガスの削減などです。また、生物多様性や再生資源化・有害物質管理なども含まれます。
社会が成長することを支援する取り組み(Social)
社会が成長するためには、それぞれの企業が支援していくことが重要と考えられています。また、個人が充実した生活を送れることも、社会問題の解決や成長を促すとしているのです。
安全性や生産性の確保やワークバランスの向上・コミュニティへの参画などの取り組みをしています。
具体的には、顧客の需要に基づいたサービスや商品の開発・成長できる分野を強化・ビジネスの国際化・長時間労働を減らす・育児休暇取得を推進するなどです。
企業統治への取り組み(Governance)
企業統治はコーポレートガバナンスと呼ばれ、さまざまなステークホルダーが企業を統制・監視することです。投資家や取引先・消費者・従業員などがステークホルダーに含まれます。企業経営を透明化して、成長させていくことが目的です。
企業統治には、コーポレートガバナンスコードに準じた経営や法規の順守が大切になります。また、グループ企業の場合は、統治体制を確立することも必要です。
具体的には、BCP対策の推進や情報セキュリティ業務の推進・教育や研修の実施・リスク対応力の強化などが行われています。
ESG経営が求められる社会背景
ESG経営が求められる社会背景については、以下のような要因があります。
経営リスクの多様化
変化が激しく先行きの予測が困難な時代にあっては、企業が直面するリスクも多様化しています。
さまざまなリスクを予測・対応していくためには、環境・社会・ガバナンスの問題に意識を向けたESG経営が注目されているのです。
ESGへの取り組みが企業の評価につながりやすいこと
2008年のリーマンショックによる株価大暴落をきっかけに、資金力など財務を重視した投資から、環境・社会・ガバナンスの課題に取り組む経営を評価するESG投資へと変化しています。
企業価値を高めるためにESG経営に舵を切る企業が増えていると言えるでしょう。
SDGsの普及
人類は貧困や紛争、気候変動など多くの課題に直面しており、その解決のため、2030年までに達成すべき目標として可決された世界共通の具体的な目標が、SDGs(持続可能な開発目標)です。
ESGに取り組むことがSDGsへの貢献につながるとして、ESG経営にも注目が集まっています。
ESGとSDGs・CSR・SRIの違い
SDGsとの違い
どちらも環境問題や雇用問題、多様性の尊重などへの取り組みという点で共通していますが、SDGsは国連・各国政府全体の目標として掲げられたものであるのに対し、ESGは企業経営に関して用いられる点で異なります。
CSRとの違い
CSRとは「企業の社会的責任」の意味で、企業は、社会の構成員として環境やステークホルダーに向けた責任ある行動が求められます。
ESGとの違いは、CSRは企業が社会に向けて果たすべき責任を示す企業目線の概念ですが、ESGは投資家が投資活動の際に重視する要素を示す投資家目線の概念になります。
SRIとの違い
SRIとは「社会的責任投資」の意味で、非財務情報を重視する投資手法のことです。
非財務情報を重視する点でESGはSRIと共通していますが、SRIが倫理的な価値観を重視することが多いとされるのに対し、ESG投資は長期的にリスク調整後のリターンを改善する効果があるとされています。
ESG経営のメリットとステークホルダーへの影響とは?
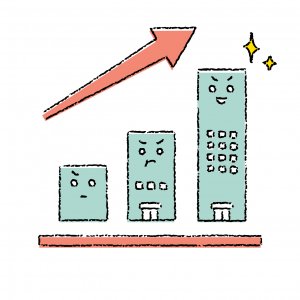
ESG経営をすることで、企業の価値を高められます。消費者や投資家などから評価される機会が増え、長期的に信頼される企業になります。特に、社会問題の解決に取り組んでいることから、宣伝やブランディングにも成功しやすいです。
また、ESG経営では、リスクを考慮した経営戦略も考えています。リスク管理のレベルが高くなると、将来的なリスクや必要なコストを想定した経営ができるのです。最終的には、長期的に成功しやすい企業になれるでしょう。
ESG経営は企業を取り巻くさまざまなステークホルダーに影響を与えます。
例えば、「顧客」には、より良いサービスや商品を届けることが可能です。
社会や環境に配慮するというESGの考え方を参考にしたサービスや商品を開発すれば、それに賛同する新規顧客が増えます。そして、顧客は自分に合ったサービスや商品を選択できるようになるのです。また、いいものを使っているという精神的な充実感や満足感も得られるでしょう。
例えば、環境を守る商品を選ぶ「グリーン消費」、環境問題や弱者への配慮を買い物で実現しようとする「エシカル消費」という消費者運動が盛んに行われています。
つまり、ESG経営は、それらの消費者運動の活性化にも貢献しているのです。
「取引先」への影響として、信頼力やブランド力のある企業と取引できるというメリットがあります。
ESG経営に取り組んでいる企業として有名になれば、短期的な利益だけでなく、長期的な利益や価値も高まる可能性が高いです。よって、安心して取引を継続できます。
また、グローバル化やチェーン店展開で利益が上がれば、取引先の仕事も増えるでしょう。
ESG経営をする企業の取引先は、取引量や収益の増加が見込めるのです。
ESG経営は「従業員」にも大きな影響を与えます。
日本の職場環境や仕組みは、長時間労働や能力開発不足など、見直しが必要なケースも多いです。労働環境に問題があると、労働意欲の低下や創意工夫の欠如などが起きて、最終的には企業の業績にも関係します。
そこで、ESG経営を実践すれば、従業員が働きやすい環境を提供できるのです。従業員のモチベーションが上がると、企業の業績も向上します。
また、1日の3分の1以上を職場で過ごす人もいるでしょう。職場の衛生的かつ精神的な環境を整備し、働きやすくすることが大切と考えているのです。
「地域社会」もステークホルダーに分類されます。ESG経営では、社会貢献の一つである「地域創生」が重要です。
雇用創出や人口定着などを目標にして、地域を活性化させようとしています。ESG経営で地域の人や障害がある人・ブランクがある人などを採用していけば、地域社会にもいい影響を及ぼすのです。
ただし、人材と資金・ノウハウがないと、円滑な企業経営はできません。
経営資源を豊富に持っている企業がESG経営で社会貢献していけば、それらの問題を解決できる可能性があります。
ESG経営の「投資家」への影響は、投資する企業を選択しやすくなることです。短期的な利益を追求する投資家もいますが、長期的な利益や成功を支援する投資家もいます。
また、環境問題や社会貢献を実践する企業を支援したい投資家もいるのです。
そのような考え方の投資家は、ESG経営をしている企業を見極め、支援するかを決めています。さらに、投資する企業への信頼感も増すでしょう。
将来的な成長や価値の向上が見込めて、満足できる投資ができます。
「政府」もステークホルダーの一つで、ESG経営によっていい影響があります。政府は「スマート社会」「超スマート社会」を目標にしていて、「Society 5.0」などを掲げました。これは、ロボットやAIなどで足りない労働力を補い、人々の負担を減らしながら、快適に過ごすことを目標にしています。
ESG経営は、生産性の確保やワークバランスの向上など、さまざまなことに取り組んでいることが特徴です。
つまり、ESG経営をする企業が増えれば、政府のスマート社会に対する目標も達成しやすくなるでしょう。
ESG経営における課題とは?
中長期的に取り組む必要がある
ESG経営は施策に対する結果がすぐに得られるものではなく、中長期的に取り組む必要があり、成果を得るまでに時間を要するという一面もあります。
成果を可視化するには、ESGのうち組織内部の課題解決となる「社会(Social)」「企業統治(Governance)」の施策を積極的に推進する方法が有効だといえるでしょう。
明確な評価基準が存在しない
ESG経営の歴史は浅く、明確な評価基準が存在しません。具体的な指標や基準は、今後ESG経営に取り組む企業が増えていくことで少しずつ明確になり、確立していくと考えられます。それまでは、自社で判断しながら取り組む必要があるでしょう。
ESG経営をする時のポイントとは?
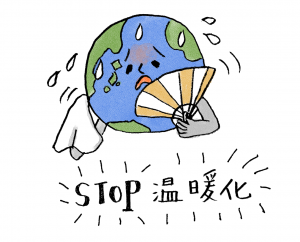
ESG経営を導入する時には、最初にESGを取り巻く環境について理解することが大切です。
長期的に続けるためには、社会貢献や環境問題・社会統治についてしっかりと理解し、経営方法の大まかな流れも把握しなくてはなりません。そして、日本政府や世界で掲げられている目標についても、詳細な知識を得ているといいでしょう。
例えば、「SDGs」「パリ協定」「サーキュラー・エコノミー(CE)」は大切です。
SDGsは国連が出している国際社会の共通目標で、2030年までに解決したいことが記載されています。個別目標は17個あり、ターゲットは169に分かれていることが特徴です。
パリ協定は「気候変動抑制」に関する国際的な協定です。
温暖化対策として、世界の平均気温上昇が産業革命以前よりも「2℃未満に抑えること」そして「1.5℃未満に抑えられる努力をすること」を掲げています。それらを実現するためには、温室効果ガスの排出量を減らしていくことが大切なのです。
また、温室効果ガスの排出量だけでなく、森林などの植物による吸収量のバランスが取れることも重要視しています。温暖化対策に取り組むためには、ESG経営で省エネやスマートエネルギーなどを意識するといいでしょう。
パリ協定についての理解を深め、ESG経営の戦略を考える上で、参考にすることが大切です。
サーキュラー・エコノミー(CE)とは、資源を再利用して、持続的に成長しようとする経済モデルのことです。
さまざまな原材料は、将来的に足りなくなると考えられています。
例えば、鉱山などから採取する金属は、消費量が埋蔵量を上回る可能性があるのです。よって、再利用できるものは再び使うことが重要になります。
サーキュラー・エコノミーの「製品や素材を再利用して使い続ける」「自然システムの再生」「環境や健康に有害なものを排出しないデザインや仕組みの確立」を意識して、ESG経営に取り入れるといいでしょう。
ESG経営を成功させるためには、企業の取締役会など、重要なポジションにいる人が積極的に実践することも大切です。ステークホルダーから求められていることを把握し、それを自社の企業戦略に反映できるといいでしょう。
また、事業戦略とESG戦略を統合することも重要です。ESGに関する内容を個別に進めるよりは、企業戦略の一つとして取り組む計画を立てます。そして、従業員にも理解してもらい、組織全体として取り組む姿勢を維持するのです。
ESG戦略に関する講習会や勉強会を積極的に実施し、組織での「ESGリテラシー教育」を充実させることもポイントになるでしょう。
ESG投資も重要なポイントの一つ
投資判断にESG経営の内容を取り入れる、ESG投資という考え方があります。企業の財務情報のみを参考に投資するのではなく、投資先のESGの取り組みをチェックして投資対象を選ぶことで、ESG課題への継続的な配慮を促します。投資を通じて、持続可能な社会の実現を目指す取り組みといえるでしょう。
ESG投資は、投資戦略として次の7つに区分されています。
ネガティブ・スクリーニング
倫理的観念や投資リスクから、武器やアルコール、タバコの事業等に関わる収入が一定以上の企業を投資対象から外す方法
ポジティブ・スクリーニング
ネガティブ・スクリーニングとは反対に、ESG関連の評価が相対的に高い企業に投資する方法
規範に基づくスクリーニング
ESG投資の国際基準を満たしていない企業を投資対象から外す方法
ESG統合
財務情報だけでなく、非財務情報も含めて体系的に分析し、投資判断する方法
サステナブル・テーマ投資
再生可能エネルギー、持続可能な農業、男女同権、ダイバーシティなどESG分野の特定テーマに特化した企業やファンドに投資する方法
インパクト投資
社会・環境に貢献する技術やサービスを提供する企業に積極投資する方法
エンゲージメント・議決権行使
株主総会や情報開示請求などを通じて、企業へESGを意識した経営を働きかける方法
これら7つの手法は、単独ではなく重複して用いられることも少なくありません。ESG経営では、ESG投資の手法を理解したうえで戦略を練ることが重要です。
ESG経営の企業事例
ESG経営に取り組む企業は年々増えております。その中で代表的な事例を3つご紹介します。
ANAグループ
ANA株式会社では持続可能な社会の実現と企業の価値向上に向けてグループ全体で取り組んでいます。すべての事業活動で安全を最優先し、ステークホルダーとの対話から経営戦略をすり合わせすることなどがESG経営の軸です。ステークホルダーとのコミュニケーションを取り組みに生かし、取り組みの結果を情報開示するというサイクルで、ESG経営を実践しています。
花王株式会社
花王株式会社では、2019年に「Kirei Lifestyle Plan」を策定し、19の重点取り組みテーマ(マテリアリティ)を選定し、それぞれで中長期の目標を定めて活動を推進しています。
「自分らしくサステナブルなライフスタイルを送りたい」という生活者の思いや行動に寄り添った経営を実践しているのが特徴です。
SOMPOホールディングス株式会社
損保ジャパン株式会社などの保険会社をグループ企業とするSOMPOホールディングス株式会社は、ESG経営に優れた企業ランキングで4年連続1位を獲得するなど、積極的な活動が評価されています。
例えばダイバーシティ&インクルージョンを、グループの成長に欠かせない重要な経営戦略のひとつと位置づけ、ダイバーシティ推進本部を設置し、2021年3月末時点の管理職に占める女性の比率は24.2%と高い水準を達成しています。
ESG経営について理解し、取り入れてみよう!

ESG経営は社会貢献や環境問題に取り組むため、企業の将来的な価値を高めることができます。企業自体の評価も高くなり、従業員や取引先・消費者からの信頼力も高まるでしょう。ESG経営をする時には、概要やメリット・関連する法規などを理解することが大切です。
これを参考にESG経営に関する知識を深め、経営戦略に取り入れてみてください。
株式会社武蔵野では、「経営計画書」の無料お試し資料をプレゼントしています。
経営計画書とは、会社の数字・方針・スケジュールをまとめた手帳型のルールブックです。
750社以上の企業を指導する株式会社武蔵野 代表取締役社長 小山昇の経営哲学が詰まった経営計画書の作成手順・作成フォーマットがセットになった充実の内容となっています!
ぜひ、こちらからダウンロードしてください。



 ポストする
ポストする シェアする
シェアする LINE
LINE この記事は約4分で読めます。
この記事は約4分で読めます。