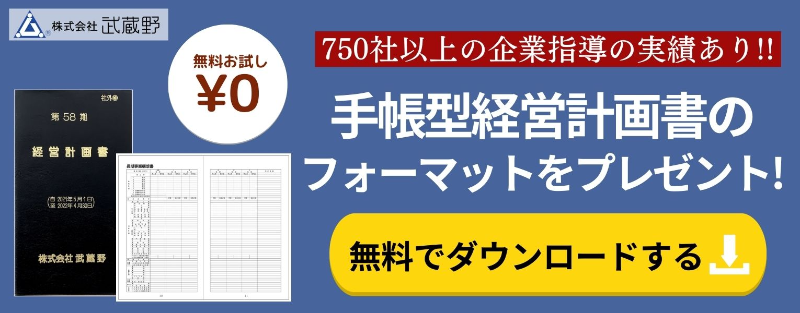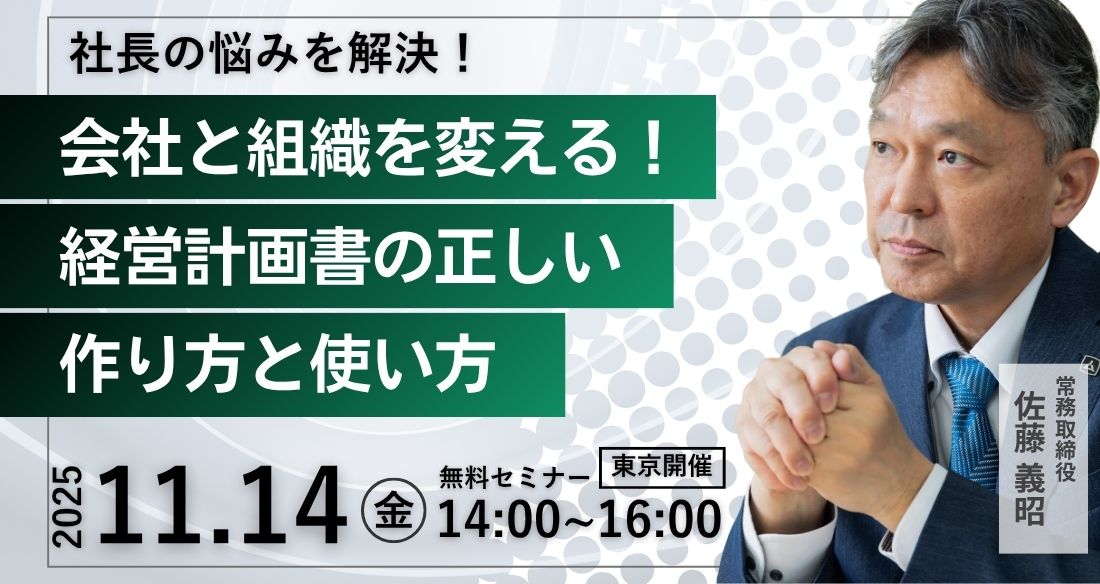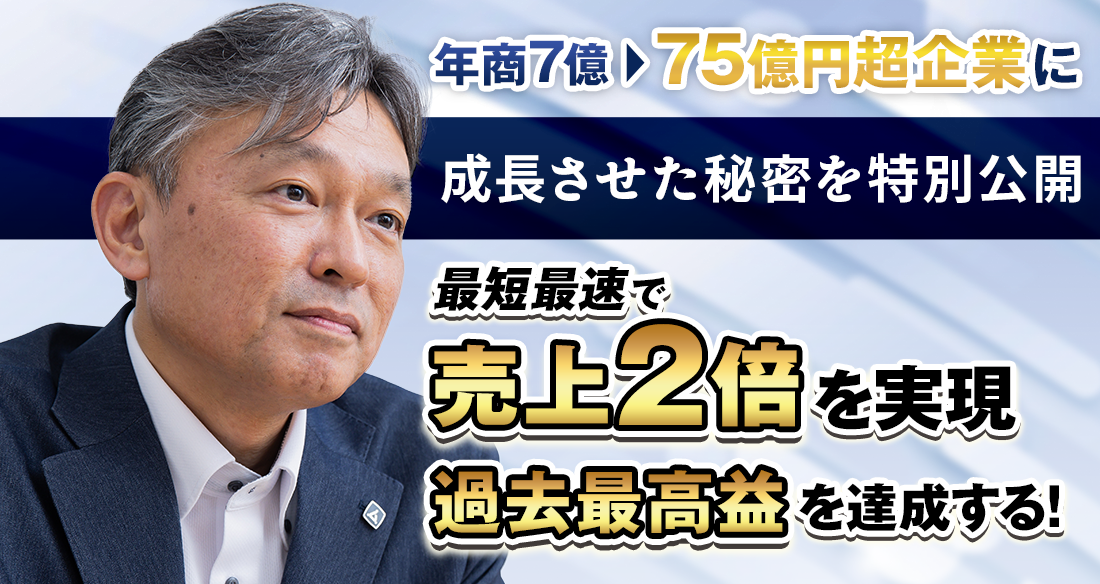ランチェスター戦略は販売競争を生き残るために用いられているマーケティング理論です。
しかし「名前は聞いたことがあるが、いまいち内容がわからない」という企業経営者も多いのではないでしょうか。
そこで本記事では、ランチェスター戦略の概要や法則、活用方法、マーケットシェア率、ランチェスター戦略を成功に導くポイントをわかりやすく解説していきます。
ランチェスター戦略とは?
ランチェスター戦略とは、世界で最も広く利用されている戦略の1つと言われており、弱者が強者に勝つための戦略方法で、中小企業が大企業に勝ち抜くために役立つ戦略です。
ランチェスター戦略の具体的な内容に入る前に、ランチェスター戦略の目的と誕生した背景について詳しく解説します。
ランチェスター戦略の目的
ランチェスター戦略は日本発祥のビジネス理論です。
企業間の販売競争で生き残る方法として「強者と弱者それぞれの立場で勝利するにはどうすればよいのか?」の分析を目的としています。
業界リーダーの大企業だけではなく、ヒト・モノ・カネ・情報のような経営リソースに乏しい中小企業にこそ、ランチェスター戦略は大きなメリットがあります。
弱者の戦略を積極的に駆使した結果、業界リーダーのポジションを獲得した企業も存在しており、現代の日本でも幅広く活用されている理論といえるでしょう。
つまりランチェスター戦略とは、強者の戦略に限らず、弱者でも利用できるマーケティング戦略の1つなのです。
ランチェスター戦略が生まれた背景
そもそもランチェスター戦略(ランチェスターの法則)はマーケティング理論ではありません。イギリスの航空大学のエンジニアであるフレデリック・ランチェスターが第1次世界大戦時に提唱した数理モデルです。
数理モデルの内容を簡単に説明すると「勝利を決定づける要因には兵力数と武器の性能があり、武器の質が同等であれば兵力の差によって勝ちが決まる」というものです。
その後、第2次世界大戦中にコロンビア大学の数学教授であるバーナード・クープマンによって軍事戦略に発展し、やがて日本でマーケティング理論として広がりました。
現在もランチェスター戦略を応用した経営理論が数多く存在しています。
ランチェスター戦略には2つの法則がある
ランチェスター戦略には第一の法則である「弱者の戦略」と第二の法則である「強者の戦略」が存在します。
それぞれの内容について解説します。
弱者の戦略【ランチェスター第一法則】
ランチェスター第一法則は接近戦や局地戦であり、限定的なエリアで剣、斧、弓矢など原始的な武器を使用する戦闘を想定しています。
つまり、一騎打ちで狭い範囲、至近距離による戦いとして以下の計算式が成り立ちます。
武器効率の質が変わらなければ兵力数で上回る側が勝利し、兵力数が変わらなければ武器効率の質で上回る側が勝利する、という法則です。
たとえば以下2つのグループがあるとしましょう。
・Aグループ=兵力数4人、武器効率2
・Bグループ=兵力数3人、武器効率3
この場合、Aグループの戦闘力は「兵力数4人×武器効率2=8」。
一方、Bグループの戦闘力は「兵力数3人×武器効率3=9」です。
このように、AグループよりもBグループの兵力が劣っているにもかかわらず、武器効率に優れたBグループのほうが戦闘力は上回る結果となります。
多数の社員を持つ大企業に社員の少ない中小企業が勝つためには、数ではなく質を高める戦略に替えればよいのです。弱者の基本戦略は差別化です。
強者の戦略【ランチェスター第二法則】
ランチェスター第二法則は広大なフィールドを想定した戦いであり、小銃やマシンガンのような近代兵器を使用する戦闘を想定しています。
つまり、集団対集団で広範囲、遠隔戦による戦いとして、以下の計算式が成り立ちます。
第一法則との違いである「兵力数の2乗」に注目して、先ほどと同じ以下の例で比較してみましょう。
・Aグループ=兵力数4人、武器効率2
・Bグループ=兵力数3人、武器効率3
第二法則の場合、Aグループの戦闘力は「兵力数4人の2乗×武器効率2=32」。
一方、Bグループの戦闘力は「兵力数3人の2乗×武器効率3=27」です。
第一法則では武器効率に優れたBグループの戦闘力のほうが上でしたが、第二法則においては、兵力数に勝るAグループのほうが戦闘力は高くなります。
これをミート戦略といい、弱者の基本戦略である差別化戦略を封じ込める意味があります。
接近戦や局地戦と異なり、広範囲の遠隔戦では兵力数がより重視されます。
つまり商品が同等であれば、社員の少ない中小企業より、量で勝っている大企業が勝利することは間違いありません。
ランチェスター戦略のメリット
ランチェスター戦略のメリットを3つ解説いたします。
弱者の戦略が明確にわかる
ランチェスター戦略では、「特定の市場においてナンバーワンを狙う」「強みがある分野に1点集中」「売上シェアは下位から奪う」と、弱者が取るべき戦略が明確に説明されているので、今後どう強者と戦っていくべきかに悩むことがありません。
強者の考え方も理解できる
ランチェスター戦略には、先ほどの段落でもご紹介した通り、強者の戦略も存在します。
強者から全面対決を仕掛けられると弱者に勝ち目はありませんが、強者が取るであろう戦略を予測し、強者の視点を持つことで、いずれ来たるべき「強者」との対決に備えるようにしましょう。
弱者でも強者に勝てる見込みがある
市場を絞り込み、強みに特化することで、中小企業やスタートアップ企業でも、ナンバーワンを狙えるといわれています。
戦時中に生まれた法則を元にした経営戦略ですが、すでに多くの企業がランチェスター戦略によって成功を収めているため、自社にも取り入れやすいのもメリットの1つです。
ランチェスター戦略のデメリット
ランチェスター戦略のみで勝てるとは限らない
ランチェスター戦略だけでは、必ずナンバーワンを獲得できるわけではありません。
経営に関する基礎知識をつけておくことはもちろん、ランチェスター戦略を具体的に実践するための知恵と工夫を手にしていることが大事です。
今の経営戦略をより強化するためにランチェスター戦略を取り入れるというスタンスで臨みましょう。
弱者と強者の立場を間違えると大きな失敗につながる
市場分析の段階で、弱者と強者の立場を間違えないことが大切です。弱者が「強者の法則」をとっても成果は上げられません。
ランチェスター戦略における強者は、「マーケットシェア率が1位の企業」のみです。
それ以外はすべて弱者となるので、その点を間違えないようにしましょう。
ランチェスター戦略の活用方法
ランチェスター戦略の第一法則と第二法則について解説しましたが、ビジネス上、どのように活用すればよいのでしょうか。
ここでは、それぞれの活用法について説明します。
ランチェスター第一法則の活用
ビジネスにおける第一法則の武器には商品やブランド力があり、ビジネス上の一騎打ち、局地戦、接近戦には次のような意味があります。
・一騎打ち=競合企業を1社に絞ったり、極めて少数のライバルしかいない市場や顧客にターゲットを絞ること。
・局地戦=限定したビジネス領域や地域を狙って自社の経営リソースを注ぎ込むこと。
・接近戦=競合企業と直接的に戦わず、顧客との距離を縮めて接触頻度などの回数を増やし、顧客に自社の印象を植え付けること。
このように第一法則では社員数や売り場面積によるライバル企業との戦いを避け、商品やブランド力によって企業価値の向上を図ることが大切です。
ランチェスター第二法則の活用
ビジネスにおける第二法則の兵力には社員数、売り場面積、豊富な資金力などがあり、ビジネス上の確率戦、遠隔戦、広域戦には次のような意味があります。
・確率戦=競合ひしめくマーケットや併売率の高い顧客を狙ったり、商品数の増加や新製品のリリース期間を早めるなど、弱者に付け入る余地を与えないこと。
・遠隔戦=豊富な資金をもとに広告宣伝を行い、顧客とのファーストコンタクト以前に自社認知度をアップして指名買いにつなげること。
・広域戦=意図的に大きな市場でビジネスを展開し、品揃えや資本力などによって他の企業を圧倒すること。
このように第二法則では一騎打ちや局地戦、接近戦を打ち消し、圧倒的な資金力によって同質化競争に持ち込むミート戦略が基本になります。
ランチェスター戦略の強者と弱者を決定づけるマーケットシェア率
ランチェスター戦略が定義する弱者と強者を決めるのはマーケットシェア率です。
業界1位の企業のみが強者であり、それ以外の企業は弱者となります。
ここでは、マーケットシェア理論とシェア率の目安について解説します。
マーケットシェア理論とは
マーケットシェア理論とは、業界内の占有率を示す指標として、ビジネスで使用されている言葉です。
主に特定したマーケットの総売上高に対し、個別企業の売上高の割合をもとに決められます。
マーケットシェア率が高い企業は市場におけるポジションが強く、ビジネス活動を有利に進められるという特徴があります。
なお、ランチェスター戦略における強者とは、市場占有率1位の企業のみを指し、2位以下の企業は全て弱者です。
ただし市場ごとの指標なので、Aという市場では弱者でも、より細分化したBという市場では強者という可能性があります。
たとえば、幼児向けおもちゃ業界全体のシェア率では弱者でも、積み木に限定すれば強者になるケースも考えられるということです。
市場で1位を取るために必要なシェア率の目安
特定の市場でトップに立つために必要なシェア率の目安には「上限目標値」「安定目標値」「下限目標値」「上位目標値」「影響目標値」「存在目標値」「拠点目標値」の7つがあり、自社のシェアがどの段階にあるかを判断できます。
上限目標値のシェア率は73.9%です。
1社が7割以上を占有している状況なので、2位以下の企業とは大きな開きがあります。
大規模なマーケットで上限目標値を達成している企業はごくわずかです。
安定目標値は41.7%です。
占有率自体は4割程度と過半数を超えていないものの、安定目標値を達成した企業は独走状態を実現しやすいといわれています。
下限目標値は26.1%です。
2位の企業と僅差のケースが多く、安定性に欠けるものの、まずは目指したい数値です。
上位目標値は19.3%です。
19.3%を確保すれば、多くの場合上位3位以内に入ることができますが、この段階では弱者の中の強者という立場です。
2割確保に近付いたら1位を獲得するための戦略に切り替えます。
影響目標値は10.9%です。
「10%足がかり」といわれ、この数値を確保すれば市場全体に影響を与える存在となり、市場参入時の目安となります。
存在目標値は6.8%です。
競合相手に存在を認められる立場になりますが、まだ市場に影響を与える力はないため、本格的な競争には巻き込まれません。
拠点目標値は2.8%です。
存在価値がほぼなく、市場参入できたかどうかを判断する程度の数値となります。
2.8%以下となれば、ランチェスター戦略を行っても生存は厳しい立場です。
営業で使えるランチェスター戦略の実務体系
ランチェスター戦略を営業の現場での実践体系に組み込むためのステップをご紹介します。
地域戦略論
地域戦略論とは、特定の地域や場所に焦点を当て、その地域でシェアナンバーワンの強者を目指す戦略です。
対象地域の市場特性や競合状況を評価し、地域の相対的な強さを把握します。
ランチェスター戦略を用いて、地域内での市場シェアを最適化する戦略を開発し、各地域に応じて異なる戦術を策定し、地域ごとに競争力を高めます。
流通戦略
流通戦略とは、製品やサービスの流通チャネルを最適化するための戦略です。
各流通チャネルの競争力を評価し、市場シェアを最適化するための適切なチャネルを選択します。
そこで製品やサービスの効率的な供給を確保し、シェアを広げていきます。
営業戦略
営業戦略とは、顧客獲得、売上最大化、収益拡大などを達成するための戦略です。
競合他社の顧客層を分析し、自社のターゲット市場と競争のポジショニングを最適化、ランチェスター戦略を用いて価格戦略を最適化し、競合他社に対抗するやり方です。
市場参入戦略
市場参入戦略は、新しい市場に進出する際の戦略です。
目標市場における競合他社の相対的な強さを評価し、市場参入戦略を検討します。
その後ランチェスター戦略を用いて、市場参入戦略を最適化し、市場シェアを獲得するための計画を策定。
競争戦略の最適化と成功に向けた戦術的なアプローチを構築するのに役立ちます。
ランチェスター戦略が向いている企業の特徴
ランチェスター戦略は、規模感やマーケットシェア率に関わらず、すべての企業で取り入れるべき戦略と思われるかもしれませんが、ここではその中でも向いている企業と次の段落にて向いていない企業の特徴を解説いたします。
ランチェスター戦略に向いている企業の特徴は以下の3つです。
・売り上げシェアをさらに伸ばしたい
・中小企業の戦い方を知りたい
・顧客満足度をさらに高めたい
売り上げシェアや顧客満足度については、ほとんどの企業が当てはまると感じるでしょう。
実際、ほとんどの企業がランチェスター戦略に向いていて、それを取り入れるべきと考えられています。
ランチェスター戦略が向いていない企業の特徴
ランチェスター戦略に向いていない企業も、ごく一部ですが存在します。
ランチェスター戦略が向いていない企業の特徴は、以下の2つです。
・市場参入から時間が経っているのにシェア率が6.8%以下
・経営戦略の基礎を学んでいる段階である
自社が強みを持つ得意分野である市場参入から時間が経過しており、「存在目標値:6.8%」に到達していない場合は、今はまだランチェスター戦略を用いて競合他社と争う時期ではない為、まずは自社セールスに注力し、「存在目標値:6.8%」の到達を目指しましょう。
また、ランチェスター戦略を活かすためには、経営戦略の基礎を身に着けていることが必要不可欠です。
経営戦略の基礎をしっかりと学び終えてから、ランチェスター戦略の習得に取り掛かりましょう。
ビジネスでランチェスター戦略を成功に導くポイント
ビジネスにおいてランチェスター戦略を成功に導くには「ニッチな市場で1位になる」「足下の敵を攻撃する」「顧客やエリアを限定して攻める」の3つがポイントになります。
ニッチな市場で1位になる
メジャーな市場で大企業に勝つのは難しいため、1位を狙うならニッチな市場にターゲットを絞るほうが成功しやすいでしょう。
小さな1位をコツコツ積み重ねることで実績が生まれ「○○商品の売上ランキング1位」などの客観的な証明を得られれば、対外的にアピールすることも可能です。
市場認知度のアップはシェア率の向上につながるため、新規顧客の獲得だけではなく、既存顧客に対しても新製品を告知しやすいでしょう。
ランチェスター戦略ではニッチな市場で1位の実績を作り、その後に別市場を狙ってビジネスを展開する、という流れが大切です。
足下(そっか)の敵を攻撃する
足下の敵攻撃とは、自社よりもマーケットシェア率が高い企業ではなく、すぐ下の企業を狙うほうが効率よくシェアの拡大につながるという考え方です。
自社よりも占有率が高い企業は製品力、ブランド力、顧客認知度に優れたケースが多く、ビジネス的に勝てるかどうかはわかりません。
自社のリソースを割いても消耗戦に陥り、結果的にシェアを奪われる可能性もあります。
一方、足下の敵は戦いやすいため、ライバル企業から自社に顧客が流れ、効果的にシェアを拡大しやすいというメリットがあります。
顧客やエリアを絞り集中的に攻める
弱者が強者に勝つには、顧客や地域といった攻めるポイントを分散せず、1つに絞って集中的に取り組むことが重要です。
複数の市場を同時に奪おうとしても、経営リソースが分散して効率的に戦うことはできません。
前述したように第一法則の戦略では、一騎打ち、局地戦、接近戦がポイントになるからです。
一方、限定した市場を狙うことで経営リソースを集中できるため、効果的にシェアを広げられる可能性が高くなるでしょう。
ただし「1つの市場に焦点を絞り続けるのは難しい」という見解もあるため、ファーストステップとして顧客や地域を絞りながら、徐々に市場範囲を広げていくことがポイントといえます。
ランチェスター戦略の活用事例
実際にランチェスター戦略を駆使して成功をおさめた事例を3社紹介します。
HIS
旅行会社のHISを築き上げた取締役会長 澤田秀雄氏は、ランチェスター戦略や孫氏の兵法を学び、自社の経営戦略に取り入れたことで知られています。
当時はパッケージツアーではなく、あえて海外向けの格安航空券を販売。
パッケージツアーにも参入後は、ターゲットを若者にしたり、旅行先をバリやセブなどに絞って営業活動を実施し、「格安ツアーといえばHIS」という地位を着実に確立して強者へと上りつめていきました。
セブンイレブン
日本のコンビニ店舗数ランキングで1位を独走するセブンイレブンは、1990年代の関西圏においては、ローソンに一歩劣る「弱者」でした。
そこで販売地域を細分化し、大阪という限定された地域に資本を集中させる戦略を取りました。そこを生活圏とする人々の認知度が上がり、大阪への出店数が300店舗を超えたころから、集客力が右肩上がりに増えたと言います。
その結果、興味関心の高まりが宣伝費用対効果の向上にも繋がり、関西圏でもマーケットシェア率トップの座を奪うことに成功しました。
トリンプ
女性用下着メーカーのトリンプは、ドイツでは「強者」でしたが、日本法人設立当初は、婦人下着市場においてワコールに遅れを取る「弱者」でした。
そんなトリンプが取った「弱者の法則」は、高級路線で知られる「強者」と差別化すべく、若者向けブランドを設立したり、専門知識を磨いたアドバイザーを全国の店舗に派遣し、接近戦を展開、ランチェスター戦略に則った戦い方で「強者」に立ち向かったことが示されています。
ランチェスター戦略について深く学べる本
ランチェスター戦略ついて深く学べる本を4冊ご紹介します。
決定版 ランチェスター戦略がマンガで3時間でマスターできる本
ランチェスターの法則を体系化し、経営戦略として日本ビジネス界に広めた故・田岡信夫氏を夫に持つ、田岡佳子氏がまとめた一冊になります。
難しい理論や情報を分かりやすい漫画でまとめているのが特徴で、誰にでも読みやすく、理解しやすい内容となっています。
書籍詳細はこちら
【新版】ランチェスター戦略 「弱者逆転」の法則
ランチェスター戦略コンサルティングの第一人者として知られる、福永雅文氏による本書は、53もの豊富な事例をもとに、現代ビジネスの場におけるランチェスター戦略の活用方法を教えてくれます。中小企業の経営者がまず読んでおきたい、ランチェスター戦略導入の手引書です。
書籍詳細はこちら
【新版】小さな会社★儲けのルール
竹田陽一・栢野克己両氏による共著である本書は、中小企業の盛衰に長く携わってきた両氏だからこそ知る、生きたノウハウが詰まった一冊です。
内容は毒舌説法で、最後まで飽きることなく読破することができるでしょう。
書籍詳細はこちら
小山昇の“実践”ランチェスター戦略 ~成果を確実に出し続ける科学的な方法
弊社代表 小山の書籍でもランチェスター戦略について事例を交えてご紹介しています。
43年連続黒字、指導企業750社超で5社に1社が過去最高益を実現する、ランチェスター戦略実践法を初公開していますので、ぜひご覧ください。
書籍詳細はこちら
ランチェスター戦略を効果的に取り入れるなら経営計画書の作成も重要

ランチェスター戦略は第一法則(弱者の戦略)と第二法則(強者の戦略)にわかれます。
第一法則は商品やブランド力によって市場を絞る戦略。第二法則は社員数や豊富な資金力などによるミート戦略です。
マーケットシェア率には3つの目標がありますが、まずは下限目標値の26.1%を目指すとよいでしょう。
実際にランチェスター戦略を成功に導くには、ニッチな市場で占有率1位を目指し、顧客やエリアを限定して足下の敵を攻めることが大切です。
ランチェスター戦略を効果的に導入する場合、自社に合った経営計画書の作成が重要です。
経営計画書の作成や環境整備、人材育成などの経営哲学を学びたい方は、株式会社武蔵野の『経営計画書』を参考にしてください。
750社以上の企業を指導する株式会社武蔵野 代表取締役社長 小山昇の経営哲学が詰まった経営計画書の作成手順・作成フォーマットの内容となっています!
ぜひ、こちらからダウンロードしてください。
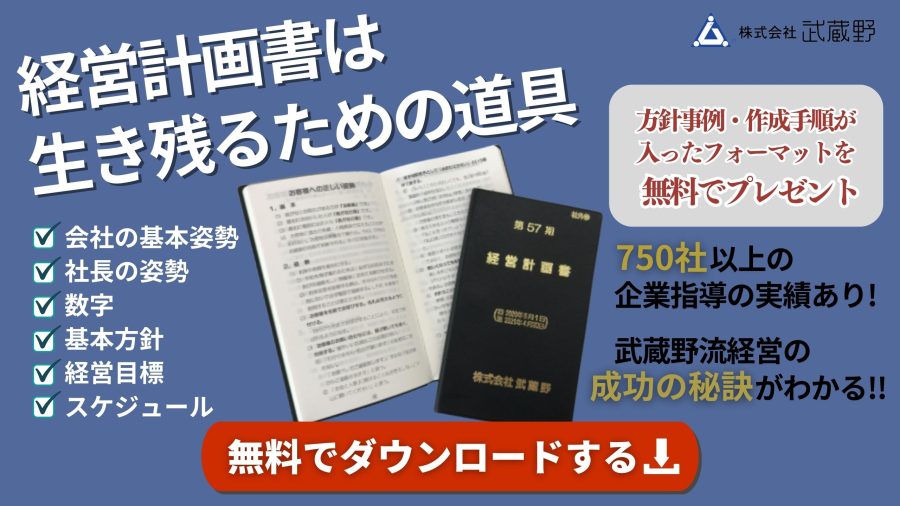



 ポストする
ポストする シェアする
シェアする LINE
LINE この記事は約4分で読めます。
この記事は約4分で読めます。