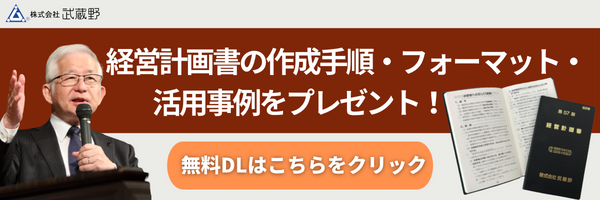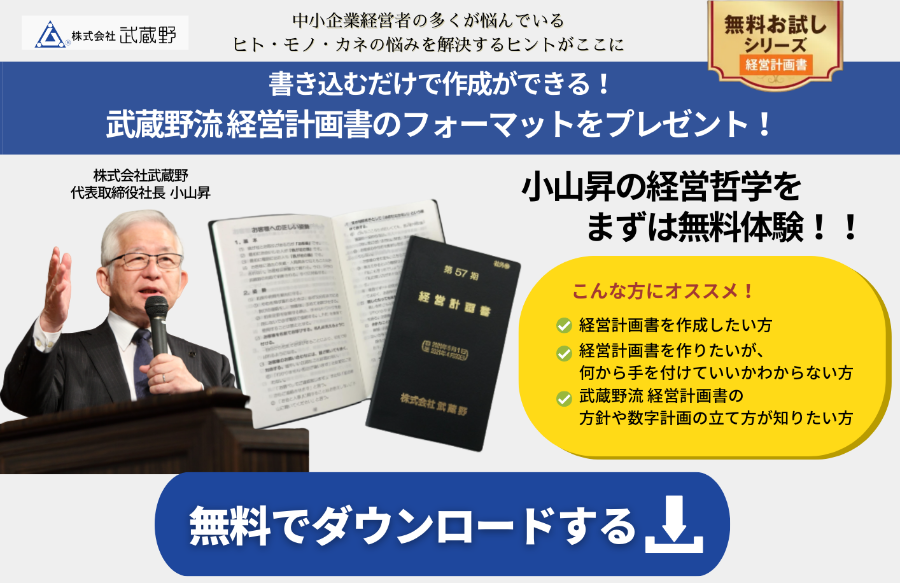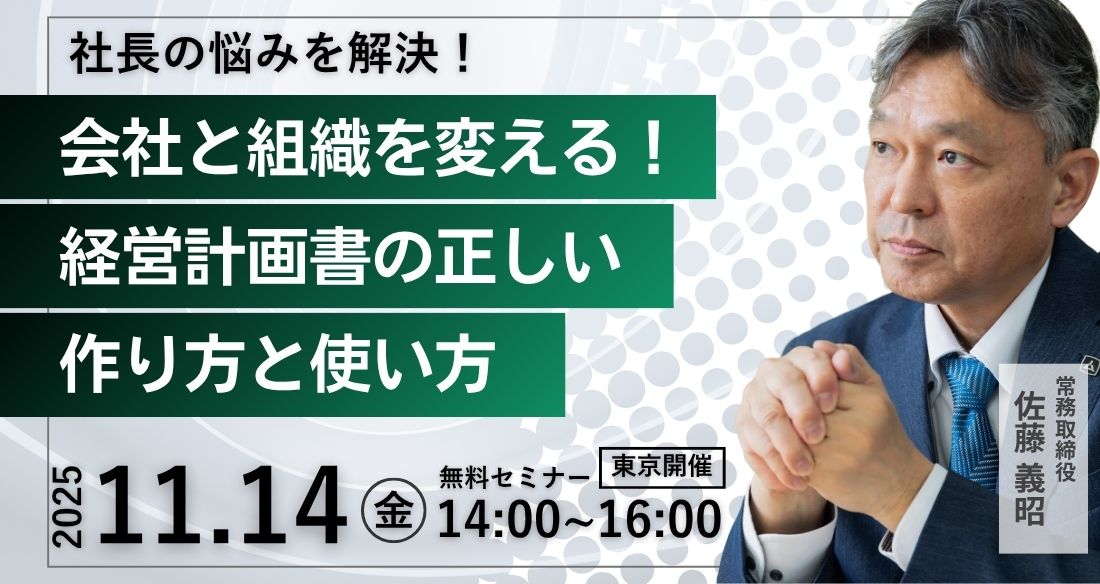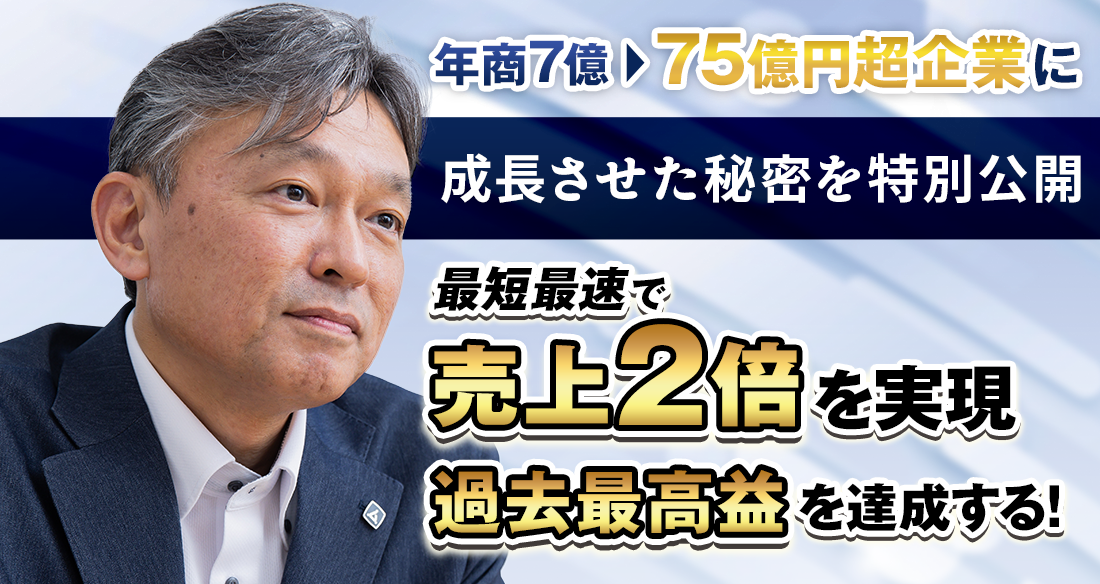日本の企業に多く見られる年功序列や能力主義の人事制度には、適切に整備しておかなければ、組織が上手く機能しなくなってしまう注意点がいくつもあります。
そして組織を無能化させる原因には、「ピーターの法則」という階層社会学も関係しているのです。
今回は企業としての組織力に大きく関わる、この「ピーターの法則」について解説します。
「昇進によって人材が無能化する」からくりを指す言葉
ピーターの法則とは、「どんなに優秀な人材であっても、一定の地位を得ることで無能化する」仕組みを示す言葉です。
もともとは1969年に発表された、アメリカの教育学者であるローレンス・J・ピーターの著書、『ピーターの法則―〈創造的〉無能のすすめ』の中で解説された内容から広まりました。
例えばとある生産現場のリーダーから、生産部門の「係長」「課長」というように昇進していく場合。
「課長」の職務内容に見合う能力がなければ、その人材は「係長」が出世の限界となり、「係長」の地位にとどまることになります。
なおかつ「係長」という肩書があることで現状に満足し、高みを目指す努力をしなくなる可能性が高いのです。
また「現場のリーダー」では有能だったものの、実際に昇進してみると「係長」の職務が適切でなかった場合も同様です。
「係長」の役目は果たさないのに、ただそのポジションに居座るだけの人材になってしまう事態も考えられるでしょう。
階層組織の中にいれば、誰でもいつかは自分の能力の限界を迎える役職まで辿り着いてしまいます。
そして成長がストップしてしまい、結果的に無能な人材となってしまう現象がどんな職場にも起こり得る、というのがピーターの法則です。
ピーターの法則が成り立ってしまう要因
それではどのようにピーターの法則が成り立っていくのか、より詳しく解説していきます。
地位を得たことによる自己満足
組織の中で一定の地位を得て、さらに各ポジションが自分の限界だと分かってしまうと、人は向上ではなく現状維持を目指すようになります。
特に降格がない組織では、一度昇進して役職に就けば、努力しなくてもそのままの地位でいられるのです。
この状況が続くことで各階層に成長が止まった人材が集まり、最終的にはまだ限界に達していない、自己成長を目指す一部のメンバーだけが機能する組織となってしまいます。
不十分な評価にもとづく人員配置
例えば「現場仕事で有能だったから管理職にする」というように、評価基準が曖昧なケースでは、実際にマネジメントに適した能力があるのか十分に見極められません。
能力に見合わない人員配置が無能なリーダーを生み出し、さらにこの無能なリーダーによる不適切な管理が続きます。
そして不適切な人員配置が継続する悪循環から、無能な人材で占められた組織構成になってしまうのです。
育成の機会が提供されていない
仕事の内容が変わって今までの能力が役に立たなくなったとしても、その都度新しい仕事内容に適したスキルを身につけられれば無能化を防ぐことができます。
つまり、人材の無能化が頻発する組織では、新たな役割に必要な能力向上の場が整っていない場合が多いのです。
特に、マネジメントに関する能力は昇進によって初めて求められる場合も多いため、組織側が事前に学ぶ機会を用意することが重要となります。
加えて、その1つ上の役割の人材が能力向上に向けてフォローをするなど、常日頃からサポート体制が構築されているかどうかをチェックしてみる必要もあります。
有能な人材が無能化するメカニズムと条件
ピーターの法則をそのままビジネスシーンに適用した場合、階層組織を構成するメンバーは職務上最高の地位に達した後、さらに昇進することで無能化します。
つまり、昇進後の地位がそのメンバーにとって「不適当」と判断される地位であることと、これ以上の昇進は望めないことを意味しています。
同時に、現在の業績を基準にしてピーターの法則を使うことで、メンバー一人ひとりが今後昇進できるかどうかの判断材料となることも意味しているのです。
ピーターの法則を防止する対策例
ではピーターの法則が成立しない組織にするためには、具体的にどのような策を講じるべきか、以下からその一例をご紹介します。
評価基準の明確化
まずは昇進の基準が明確にされていないと、適切な人員配置はできません。
なぜなら上司の個人的な考えや部下との人間関係など、余計な要素が評価に加わってしまうためです。
管理側の主観による評価が続けば、本来の職務に必要な能力を持つ人材が正しく機能しなくなってしまいます。
結果として、例え有能でなくても組織内で上手く立ち回れる人材がリーダーとなり、不適切な人事が続き、ピーターの法則が成立するようになるのです。
こうした事態にならないためには、各役職にはどんな能力が必要なのか明確にし、正しい判断基準で評価する必要があります。
成長を促す機会の創出
ピーターの法則が成り立つ大きな原因の1つは、ただ1度の評価から更新されない点です。要するに降格がないために、何の成果を出さなくても良い状態ができてしまいます。
そして成長意欲がなくなり、昇進した時点では優秀だった人材が無能化してしまうのです。
そこで企業として取り組むべきなのが、一人ひとりが能力を磨き続けるための工夫。
評価制度の見直しはもちろん、管理職向けの教育やスキルアップ支援の実施など、それぞれが成長を意識できるような体制を構築することでピーターの法則を防ぎます。
降格させる
「降格条件」を定めた上での昇進であれば、もし昇進後に期待したパフォーマンスが発揮されない場合は前の役割からやり直す事が可能です。
もちろん新たな役割に慣れるまでは、昇進後にパフォーマンスを出せない期間もあるでしょう。社内でどの程度の期間まで「猶予期間」とすべきか、その目安を持つ事も大切です。
仮に猶予期間を経ても無能化が続いている場合、降格を検討する事になります。
その際には、先に本人に降格のリスクを周知する事が大切です。突然降格を言い渡されるとモチベーションダウンになりますが、猶予期間を設定し、
それでも成果が出ない場合は、降格を実行するという合意を取ると良いです。
また仮に降格を実行した場合、今後のキャリアプランや役割復帰の条件を併せて提示する事が重要です。
仮にマネジメント適性がなくても、別のキャリアパスを用意するのも1つの手段となります。
関連する3つの法則
ピーターの法則には、関連した法則が3つあります。3つの法則をご紹介します。
ディルバートの法則
1つ目は、ディルバートの法則です。
ディルバートの法則は「無能な人に地位を与えることで、現場の被害を最小限にとどめる」という説を提唱しています。
地位が上の人は、組織の運営・生産性にほとんど関わっていない為、顧客の対応や製品の生産など大部分の仕事は、現場の人によってなされているとも述べられています。
同じ組織内で、ピーターの法則とディルバートの法則の両方が同時に成り立つ場面も少なくありません。
パーキンソンの法則
2つ目は、パーキンソンの法則です。
パーキンソンの法則とは、イギリスの歴史学者・政治学者シリル・ノースコート・パーキンソンが提唱した説で、以下の2つがよく知られています。
第一法則:仕事の量は、完成のために与えられた時間をすべて満たすまで膨張する
人数が増えたことによる一人ごとの仕事量は減少するが、労働時間の減少には繋がらないとしています。
第二法則:支出の額は、収入の額に達するまで膨張する
「人は時間やお金といったあらゆる資源を、あればあるだけ使ってしまう」ことを意味しています。
ハロー効果
3つ目は、ハロー効果です。
ハローとは「後光」などを意味する言葉で、「1つの特徴に影響を受けて、対象をゆがめて見てしまう」という人間の心理を指しています。
「有名大学を卒業」「身だしなみが整っている」など、本来ビジネススキルを備えていることとは別の要素に引きずられて全体評価をしてしまうことがあります。
昇進に繋がる人事評価も、人が人を評価するシステムであるため、このハロー効果と無関係ではいられません。
社内制度によってピーターの法則は食い止められる
各人の能力を「昇進」だけでなく「昇給」で評価する、数値化して管理して明確な判断基準を確立するなど、より的確なポジショニングができる体制にすることで、ピーターの法則は回避できます。
またどんなに優秀な人材であっても、不適切な職務や置かれている環境次第では、ピーターの法則によって無能化してしまう可能性がある認識もしておかなければなりません。
組織全体の無能化を防ぐためには、まずはピーターの法則にならない企業としての土壌が必要です。
武蔵野の『経営計画書』では、750社を超える支援実績から導き出された独自の経営ノウハウを公開しています。
ぜひ、こちらから無料の資料をダウンロードしてください。



 ポストする
ポストする シェアする
シェアする LINE
LINE この記事は約2分で読めます。
この記事は約2分で読めます。