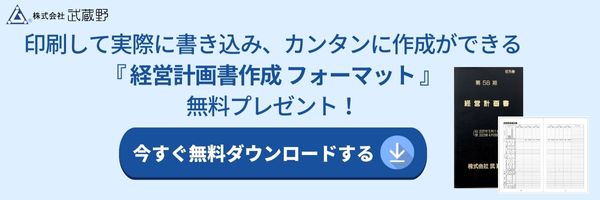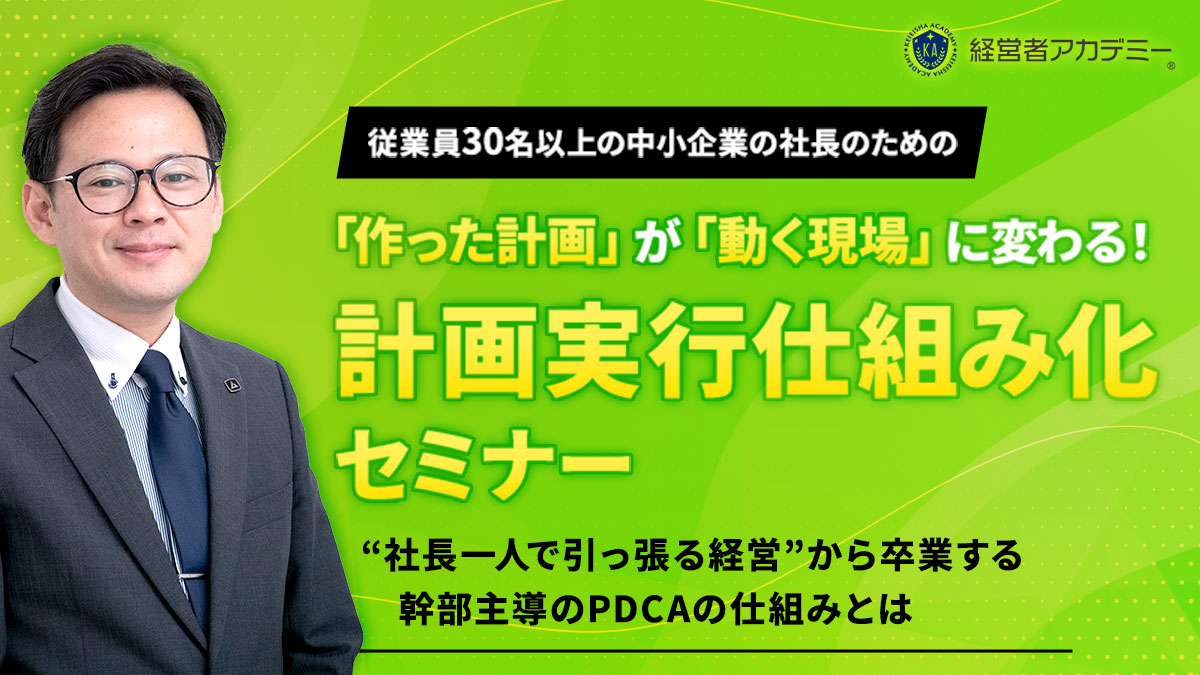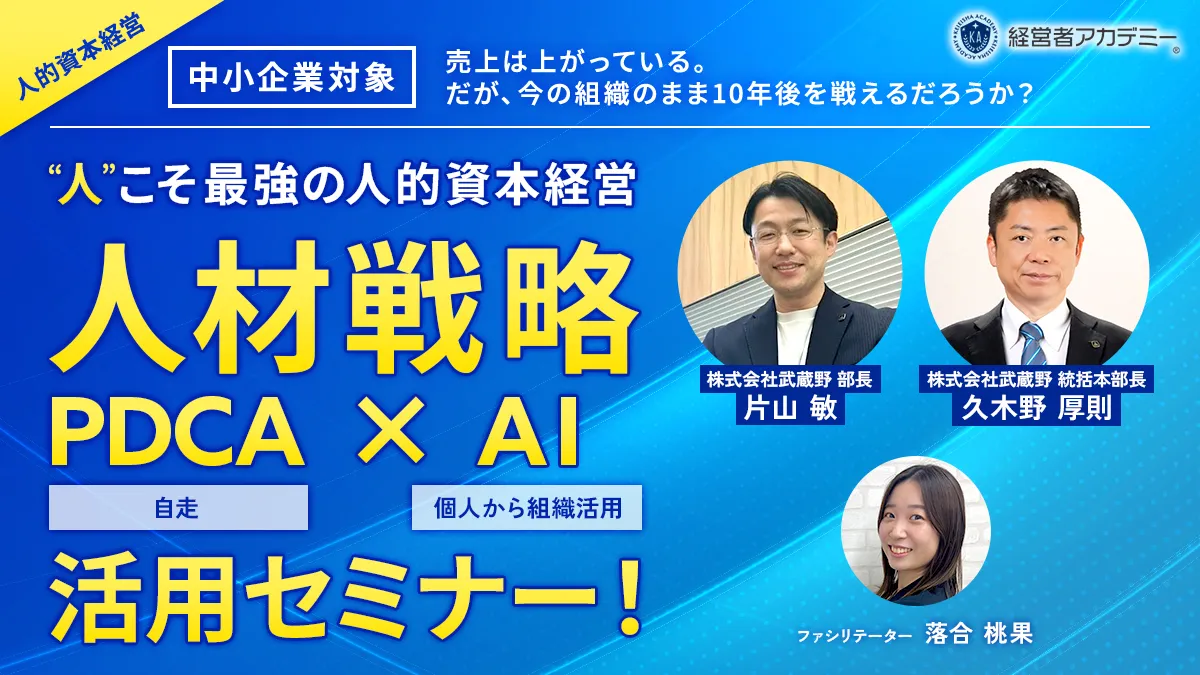運転資金は、会社を運営するにあたって必ず必要になる資金です。
運転資金がないと会社は必要な資材も購入できず、販売もできません。
会社を運営するために必要なお金ですから、経営者は自社の運転資金や考え方をしっかり把握しておく必要があります。
運転資金の重要性について解説しましょう。
運転資金とは
運転資金とは、会社やお店が「事業を行うために必要な資金」のことです。
企業が事業を維持していくために必要な商品の仕入れ、従業員の給与、広告など、事業運営をしていく中でかかるさまざまな費用をまかなう手元資金を「運転資金」と呼んでいます。
飲食店であれば、営業するためには食材を仕入れて従業員を雇い、料理を作らなければなりません。
運転資金が不足すれば、仕入れができない、人件費や家賃、光熱費が払えない、といった危機に陥り、事業継続が困難になりかねません。
これは、大企業でも基本的に同じです。
経常運転資金とは?
一般的に「運転資金」と言われるものは、「経常運転資金」のことを指します。
経常運転資金は、所要運転資金・正常運転資金とも呼ばれます。
会社を運営していくために通常必要となる資金で、仕入費用や人件費は経常運転資金に分けられ、資金が不足すると会計上は黒字でも倒産するリスクがあります。
経常運転資金に関してはこちらの記事でも詳しく解説されています。
あわせてご確認ください。
経常運転資金とは?計算方法や不足する要因、調達方法を解説|株式会社パラダイムシフト – DX×M&Aで、革新を促す
運転資金の考え方
運転資金は、日々の事業を続けていくために必要となるお金です。
商売が続けられるかどうかは、日々の運転資金が確保できるかどうかで決まります。
取引先企業と取引をする際には、先に仕入れて支払いは後で行う「信用取引」が多く行われています。
そのため、入金と支払いの間で足りない資金を補うのが運転資金です。
運転資金の計算方法
運転資金は以下の計算式で算出することができます。
「経営運転資金 = 売上債権 + 棚卸資産 - 仕入債務」
運転資金にはいくつかの種類がありますが、ここに挙げた計算式の考え方は、その中の「経営運転資金」を算出するための式です。
経営運転資金とは仕入れや人件費、家賃など毎月必要になる資金のことです。
売上債権
上記の計算式で、売上債権というのは売掛金や受取手形のことを指します。
飲食店の場合、今月仕入れた食材の代金を来月末に支払うとすると、その支払いが行われるまでの間は売上債権となります。
棚卸資産
棚卸資産とは在庫のことで、まだ売れない商品や作りかけの商品、材料、食材、消耗品などです。
つまり、店舗にある価値のある資材のことです。
仕入債務
仕入債務とは、買掛金や支払手形のことです。
飲食店であれば、今月仕入れた食材の代金を来月末に支払うなら、それまでの間は仕入債務となります。
これらの計算式の額が大きければ大きいほど、運転資金は必要になります。
額が小さかったりマイナスであれば、未回収額が少ないため、運転資金の必要性は低くなります。
次に必要になるのがこの計算式です。
「経営運転資金回転期間 = 経営運転資金 ÷ (1年の売上高 ÷ 12ヵ月)」
これは、会社や店舗の経営運転資金が、売上高の何カ月分に当たるか計算する式です。
上記の2つの計算式を使って、運転資金がどれだけかかるか把握しておかないと、健全な経営はできません。
運転資金の内訳
運転資金は、変動費と固定費の2つの要素で構成されます。
変動費
変動費とは、生産量や販売量の変動に応じて変動する費用のことを指します。
具体的な例としては、原材料費、労働費、製造費用などが挙げられます。
生産や販売の規模が大きくなれば、これらの費用も増加し、逆に生産や販売の規模が縮小すれば、これらの費用も減少します。
変動費は主に直接的に生産や販売活動に関連する費用です。
固定費
固定費とは、生産量や販売量の変動に関係なく一定の金額が発生する費用のことを指します。
具体的な例としては、家賃や給与、事務所維持費などがあります。
固定費は、事業の規模や活動量が変動しても一定の金額がかかるため、企業の収益や利益に直接的な影響を与えます。
企業は動費と固定費を把握し、経営の効率性や収益性を評価するために、それぞれの費用を適切に管理する必要があります。
運転資金の種類
運転資金は上記の二つに大きく分類できますが、具体的にどのような項目が含まれるか1つずつ説明しましょう。
これらの費用は、売掛金が入ってくるまでのタイムラグの間にも支払いが発生するものですので、それぞれの項目を把握し、あらかじめ必要な運転資金を計算しておきましょう。
経営運転資金
会社が今と同じように、営業活動をしていくのに必要な運転資金です。
常に必要な仕入れの費用や人件費、光熱費、家賃などがこれにあたります。
運転資金とは、多くの場合この経営運転資金のことを指します。
増加運転資金
売り上げが増加したなどの理由で、経営運転資金を増資するのが増加運転資金です。
飲食店の場合、お客が急増して食材の仕入れを増やすなどのために、従来より多くかかる仕入れ資金がこれに当たります。
このように、店が繁盛したり会社の売り上げが増えるのに伴って、必要になる追加費用のことです。
減少運転資金
増加運転資金とは反対に、事業不振で売上が減少しているときには減少運転資金が必要です。
売上が減っても、人件費や家賃といった固定費は支払わなければなりません。
それらの支払いに充てるいわば「つなぎ資金」となるお金が減少運転資金です。
企業は減少運転資金をつなぎとしてキャッシュフローを回しつつ、売上を増やし人件費や諸経費を削減し、経営を建て直さなければなりません。
長くこの状態が続けば、減少運転資金がショートして経営不振に陥ってしまうため、なるべく早期の回復を目指す必要があるでしょう。
賞与資金
従業員に賞与を払うために必要な資金です。毎月かかる人件費に加えて、賞与月に必要になります。
決算資金
決算時に必要な資金です。税金や株式配当、役員賞与などのことです。
季節資金
季節によって増える資金です。
飲食店で夏にビールの売り上げが2倍になるなど、季節によって増える売り上げのための仕入れ資金です。
その他運転資金
上記のどれにも該当しない運転資金です。赤字補填や買掛金の支払いなどの費用も含まれます。
運転資金が6種類あることを把握しておかないと、予想外のことで突然お金が必要になり、資金繰りがうまくいかなくなることがあります。
運転資金と設備資金の違い
運転資金と混同されがちなものとして設備資金があります。
設備資金とは、企業にとって長期的に経済的効果が期待できるものや、資産価値のある設備や機器などを購入するための資金です。
例えば、工場や店舗の拡張・増設、新しい製造機器の導入、システム開発費用など、これらのためにかかる費用が設備資金です。
運転資金は企業の運営のために必要な費用ですが、設備資金は決算上では企業の「資産」とみなされます。
決算書を作成する際に、運転資金と設備資金は異なる資金として区別されますので、ご注意ください。
運転資金の目安
では、運転資金はどれくらい用意しておけばいいのでしょうか。
業態や経営状況にもよりますが、運転資金は粗利益の3〜6カ月分くらいの余裕を持っておきたいものです。
粗利益の6か月分というとかなりの金額になりますが、会社や店舗を運営していると、どんなアクシデントが起こるかわかりません。
急激に売り上げが落ち込むこともあり得ますから、数カ月くらい耐えられるほどの資金が必要です。
しかし、資金調達力がある会社なら、1〜3か月程度の余裕があればやっていけるでしょう。
この場合の資金調達力とは、親会社の下で店舗を営業しているような場合を指します。
例えば、食肉卸の会社が運営する焼き肉店などの場合は、資金的に厳しくなれば親会社を頼ることができます。
しかし、こういったパターンは少ないので、粗利の3〜6カ月くらいは必要だと考えたほうが、安定経営につながります。
運転資金の調達方法
では、運転資金が必要なのに社内では用意できない場合にはどうすればいいのでしょうか?
運転資金の調達方法は、主に以下のようなものが考えられます。
・銀行からの融資
都市銀行や地方銀行といった銀行に融資を申し込みます。
・日本政策金融公庫からの融資
日本政策金融公庫は、政府が100%出資する金融機関で、創業融資や運転資金融資以外にも、災害復興やコロナ感染対策など政策に関わる融資制度があります。
個人事業主や小規模事業者でも相談しやすく、条件を満たせば無担保、無保証人での融資を受けられ、金利も比較的低金利です。
・自治体などの制度融資
都道府県、市区町村の融資制度を利用して融資を申し込みます。
・ビジネスローン
銀行、ノンバンクなどが事業資金用に提供しているローンを利用して融資を申し込みます。
銀行からの融資の場合は1ヶ月前後かかる場合もありますが、ビジネスローンの場合、銀行でもおおよそ3〜5営業日、ノンバンクなら即日融資を受けることができます。
しかし金利が高いことがデメリットです。
・親族や知人からの借り入れ
個人的に依頼をして借り入れます。
金利の負担はありませんが、返済が滞った場合には人間関係に悪影響が出る可能性がありますので気を付けましょう。
審査に通るか、融資限度額が必要な資金額に足りるか、返済に無理がないかなど、条件にかなう融資元を探しましょう。
運転資金をしっかり確保して健全な運営を心がける
運転資金とは、会社や店舗運営などに必ず必要なお金のことです。
例えば、飲食店なら家賃、光熱費、仕入れ代金、従業員の給料などです。
通常、運転資金は粗利の3〜6カ月分くらい持っていないと、会社や店舗の健全な経営ができません。
会社や店舗運営には急激な売上の落ち込みなどがあるので、それくらいの余裕がないと耐えきれずに倒産する可能性があります。
また、帳簿上は黒字でも、手元にキャッシュがないと倒産することがあります。
黒字倒産について詳しくは下記記事を参照ください。
黒字倒産とは?原因や回避する方法・事例をわかりやすく紹介
運転資金について今一度理解し、自社の資金繰りを見直してみてください。
株式会社武蔵野では、会社の数字、方針、スケジュールをまとめた手帳型のルールブックである「経営計画書」を活用した経営を行っております。
現役社長小山昇自らの経験体験に基づく経営ノウハウを、ぜひこちらから無料でダウンロードください。
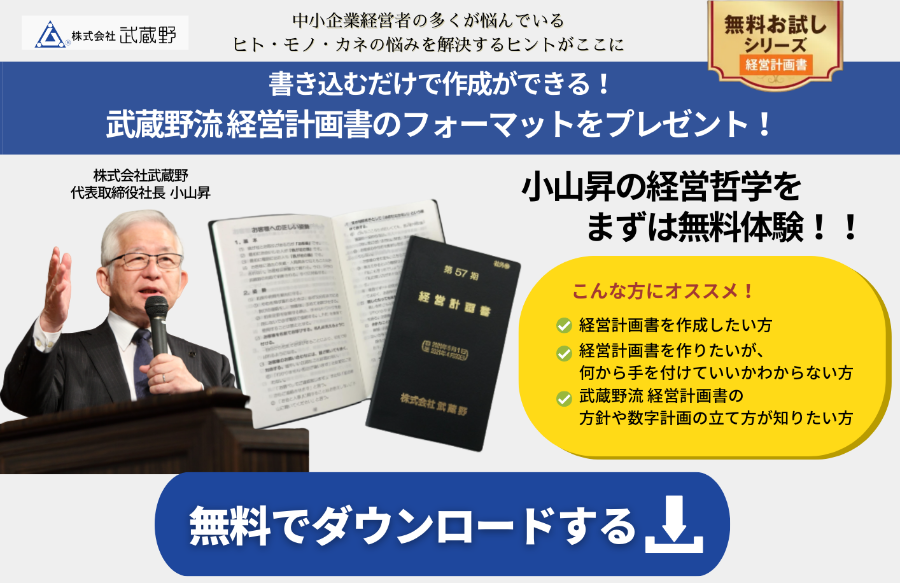



 ポストする
ポストする シェアする
シェアする LINE
LINE この記事は約4分で読めます。
この記事は約4分で読めます。