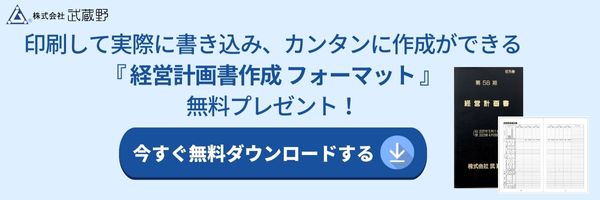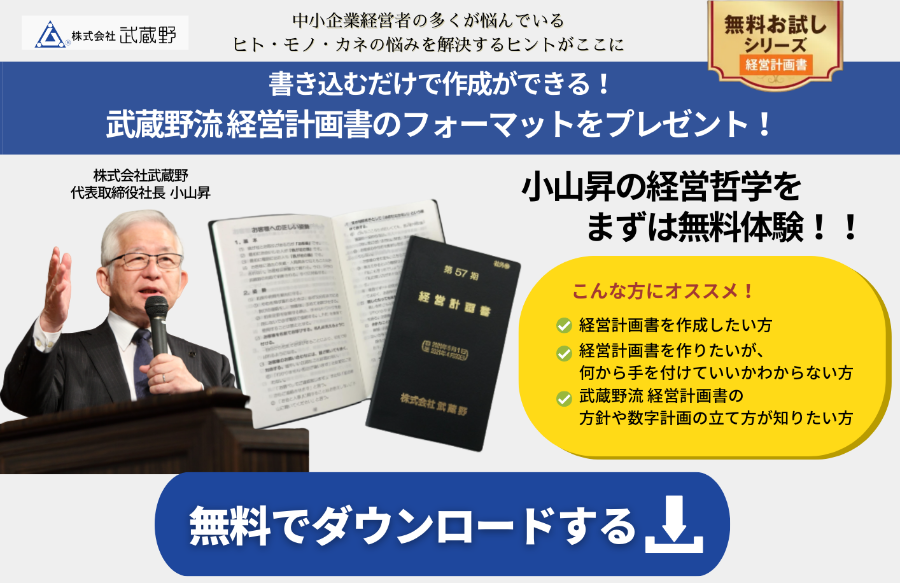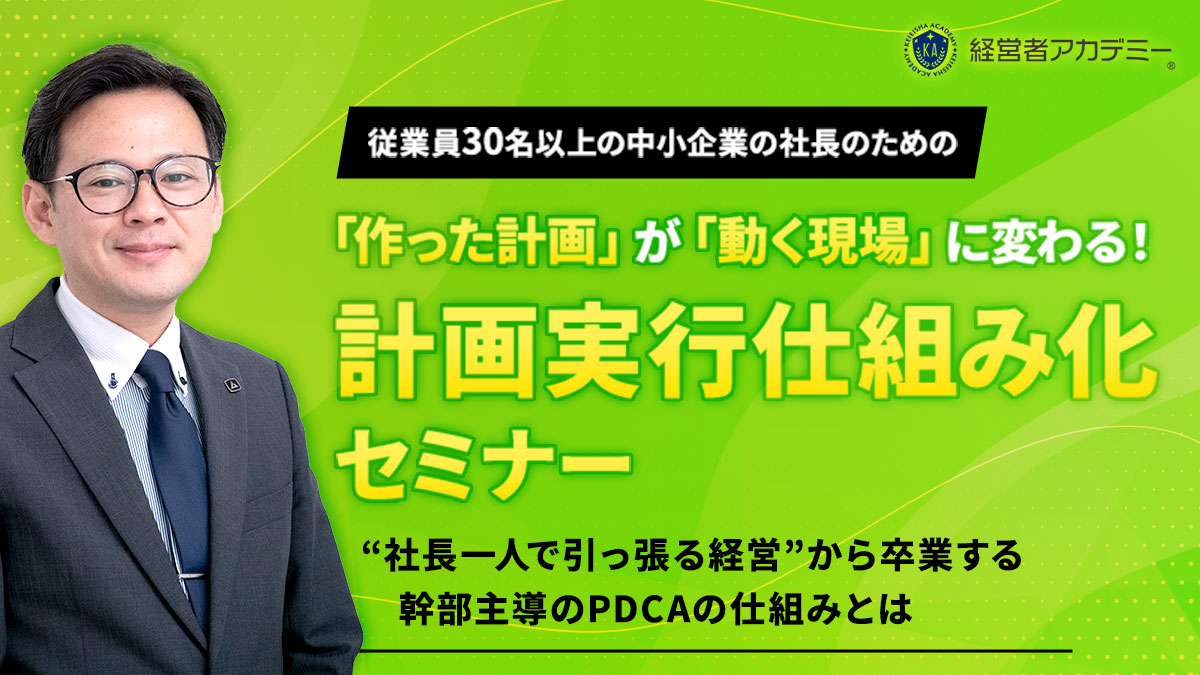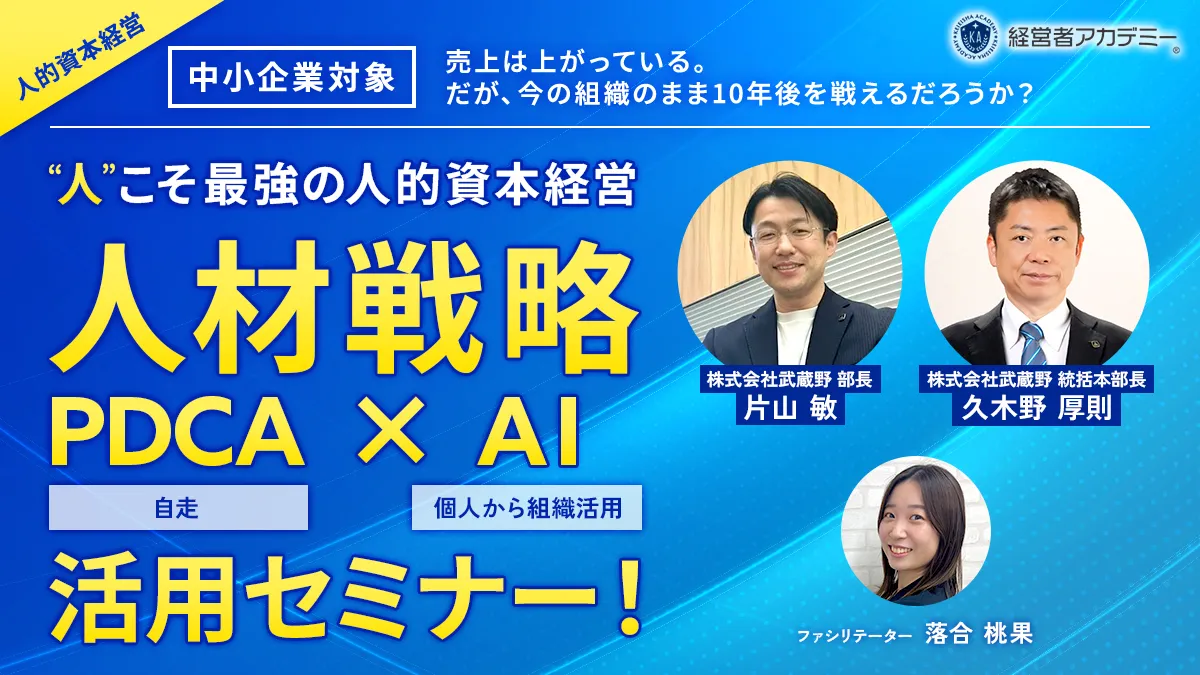事業を円滑に進めるためには、ビジネスモデルに合った売上高と人件費の比率を適切に把握することが重要です。
そのために役立つのが「労働分配率」です。
労働分配率を正しく理解することで、より実態に即した経営判断ができるようになるでしょう。
労働分配率とは
労働分配率は、付加価値に占める人件費の割合を示す指標です。労働分配率が高いということは、人件費に割く費用が多い状態を指します。
単純にいえば、給料が高い会社、あるいは機械などの設備ではなく、人的資源への依存度が高い会社です。
人件費について詳しくはこちらの記事をご覧ください。
人件費率の計算方法は?労働分配率との違いや適切な算出方法など詳しく解説
例えば、サービス業を主力事業とする会社は、労働分配率が高くなりがちです。
一方、積極的な設備投資による自動化・省力化を進めている企業においては、人件費ではなく、設備の減価償却費のほうが多くなるため、労働分配率は低くなる傾向にあります。
上記のことからもわかるように、労働分配率が高ければ良い、あるいは低ければ悪いという単純なものではありません。
それぞれの事業形態に合った、適正な労働分配率が達成されているかを見ることが重要です。
ここでいう人件費には、従業員の給与や福利厚生費などだけではなく、経営側の役員報酬なども含まれます。
労働分配率が適切だからといって、必ずしも従業員が適切な給与をもらっているとは限りません。
さらに、分母となる付加価値の大きさによっても、労働分配率は変化することも頭に入れておく必要があるでしょう。
企業にとって、労働分配率は重要な経営指標として役立つものです。まずは、自分たちのビジネスモデルに即した、適切な値になっているかを確認しましょう。
労働分配率の計算方法
労働分配率の計算式は、以下のとおりです。
「労働分配率=人件費÷付加価値(売上総利益・粗利益)×100」
たとえば、売上高が年間1億円で粗利益が4,000万円、人件費に2,500万円かかっている企業があったとしましょう。
計算式は、「2,500万円÷4,000万円×100」となり、労働分配率は62.5%です。
計算の際には、「付加価値」と「人件費」について正しく理解しておきましょう。
付加価値とは
付加価値とは、ざっくりいえば売上総利益(粗利益)のことです。
付加価値の計算方法は、大きく日銀方式の加算法と、中小企業庁方式の控除法の2種類に分けられます。
加算法は、経常利益や人件費、減価償却費といった付加価値をすべて足していく方法です。控除法では、売上高から材料費や外注費などの外部購入価値を差し引いて計算します。
しかし、いずれも計算方法は非常に複雑になってしまうのが難点です。ここでは単純に、付加価値は粗利益としてとらえておいて問題ないでしょう。
人件費とは
一方、人件費とは、企業が持つ分配可能な付加価値のうち、どれくらいが労働力として支払われているかを示すものです。
ここでいう人件費とは、役員の報酬やアルバイトの給与はもちろん、退職金や退職年金の掛金、ボーナス、従業員の教育費用、法定福利費なども含まれるので、忘れず計算に入れておきましょう。
労働分配率と労働生産性
労働分配率を考える際に、よく一緒に用いられる指標が「労働生産性」です。
労働生産性とは、従業員1人当たりの付加価値のことです。
労働生産性の計算式
労働生産性は、次の計算式で求めることができます。
労働生産性(円)=付加価値÷従業員数
労働生産性が高ければ高いほど、従業員1人あたりの付加価値が高く、投入された労働力が効率的に利用されています。
中小企業と大企業では労働生産性に大きく差があり、労働生産性は企業の稼ぐ力を表しているとも言えます。
人件費を考える場合には、労働分配率と労働生産性の両方に目を向け、どちらも向上できれば生産性の向上につながります。
【業種別】労働配分率の目安とは
労働分配率は、会社規模や業種ごとに差があります。
経済産業省が公表している主な業種の労働分配率の目安は以下の通りです。
飲食業・飲食サービス:78.8%
製造業:54.5%
電気・ガス業:33.7%
情報通信業:61.6%
卸売業:54.1%
小売業:55.8%
クレジットカード業・割賦金融業:35.4%
全業種平均:52.7%(2022年度)
労働分配率の目安は50%前後が目安と言われており、70%以上になると利益を圧迫して厳しい経営を余儀なくされると言われています。
業界別でいえば、飲食業のような接客業ではヒトそのものが重要であり、人件費をかけなければならない労働集約型の産業であるため労働分配率が高くなる傾向が見て取れます。
一方金融系事業では、人件費よりもシステム投資への投資額が大きくなる結果、労働分配率の平均値は全業種平均より大幅に下がります。
スーパーやコンビニ、消費財卸売業などは50%程度です。製造業でも自動化・省力化が進んでいる資本集約型の場合は、労働分配率が40%になることもあります。
自社の労働分配率と全業種の平均値を比較することで、適正な状態か判断する材料にもできますが、労働分配率は業種だけでなく、
個々のビジネスモデルにも大きく左右されるため、自社の労働分配率が業界の平均と違うからといって、すぐに危機感を持つ必要はありません。
実際、同じ業種内でも、会社ごとの労働分配率には開きがあります。
しかし、あまりにもかけ離れている場合は、経営に何らかの問題が生じている可能性もある為、
無駄な人件費の支出がないか、人的資本への投資は適切か、定期的に見直すことが重要です。
労働分配率の適正な数値
前章でも解説しましたが、「労働分配率」は高ければ良い、低ければ悪いといった性質のものではないことに注意する必要があります。
「労働分配率」が高ければ従業員の満足度や士気は上がるものの、人件費高騰により経営圧迫にもつながります。
企業規模によって数値は大きく異なり、大企業であれば50%ほど、中小企業であれば70%ほどが平均値です。
一方で、利益の割に給料が低すぎるなどの労働環境下では社員の離脱が増える可能性があり、どちらに偏っても良くありません。
重要なのは、その時々の自社の状況において、適正値かどうか、バランスが取れているかという点です。
参照:中小企業庁 労働生産性と分配
労働分配率を適正に保つ施策
では次に労働分配率を適正な数値に維持する施策について3つ解説していきます。
労働の生産性を高める
近年、インフレ政策や少子高齢化による労働人口の高齢化、同一労働同一賃金の実現といった要因を背景に、1人あたりの人件費が上昇しています。
企業の外的要因を踏まえ、労働分配率を適正に保つためにも1人あたりの生産性を高めるとよいです。
ボーナスや賞与の制度を明確にする
ボーナスや賞与の制度に関するルールを明確に設けると、企業業績に見合った労働分配率のコントロールが容易になります。
従業員も自身の働きを賞与で評価されるため、モチベーションが高まります。
社員モチベーションを上げる
労働分配率が低いとき、給与水準が低く、社員のモチベーションが下がり、優秀な人材を失う可能性が考えられます。
その場合、経営状況を観察しながら、人件費を可能な限り増やし、従業員のモチベーションを高めていきましょう。
また労働分配率が高い場合は、人件費の割合が高いことを示しているので、従業員の満足度は高く、モチベーションが保たれる為、将来的な成長につながりやすくなります。
しかし、人件費が企業の負担になっている可能性があり、経営の維持が困難になるリスクが高まります。
人件費を減らすために給与を減らせば、従業員のモチベーションが下がってしまうので、
従業員のモチベーションを維持しながら人件費を減らすためには、粗利益を増やすことが効果的です。
粗利益を最大化すれば、粗利益に対する人件費の割合が減少します。その結果、労働分配率が下がります。
経営の問題を追及して最大限の利益を
労働分配率は、企業において生産された付加価値全体のうち、どれくらいが人的資本に分配されているかを知るために必要不可欠な指標です。
労働分配率を正確に算出して管理することで、経営改善にも役立つでしょう。
現状の課題を解決し、今後さらに業績を伸ばしていくためにも、自社の業種やビジネスモデルから、適正な労働分配率を考える必要があります。
今回の記事を参考にして、労働分配率について、今一度見直してみてはいかがでしょうか。
株式会社武蔵野では、経営コンサルティング事業や経営サポート事業、社長のサポート事業などを展開しています。
豊富な実績に基づく経営計画書の作り方にも定評があり、これまでに400社以上の会員企業が過去最高益を達成しています。
株式会社武蔵野では、「経営計画書」の無料お試し資料をプレゼントしています。
経営計画書とは、会社の数字・方針・スケジュールをまとめた手帳型のルールブックです。
750社以上の企業を指導する株式会社武蔵野 代表取締役社長 小山昇の経営哲学が詰まった充実の内容となっています!
ぜひ、こちらからダウンロードしてください。



 ポストする
ポストする シェアする
シェアする LINE
LINE この記事は約3分で読めます。
この記事は約3分で読めます。