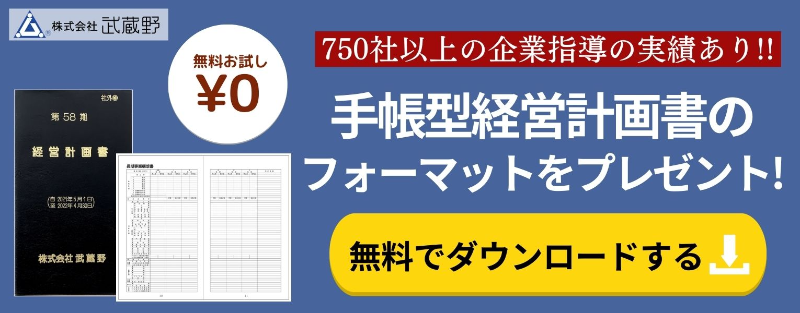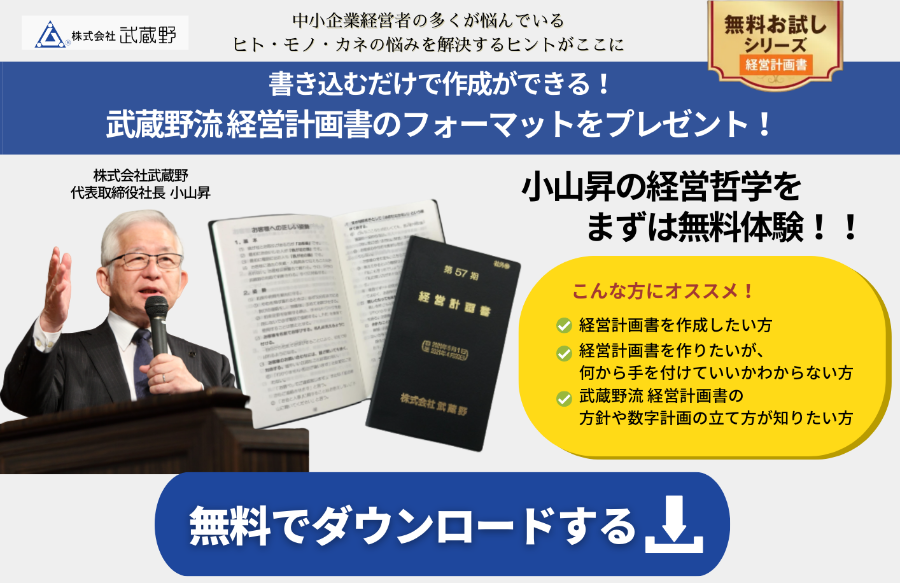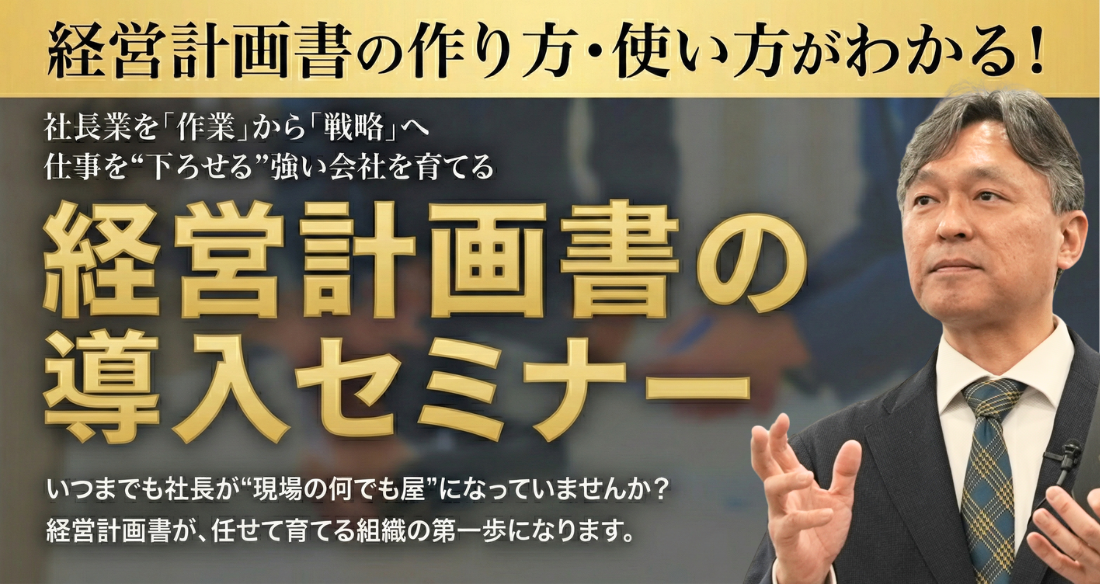高いやる気を持って業務に取り組んでいた従業員が、急にモチベーションを失い、まるで別人のように仕事への情熱を失ってしまうケースがあります。
その原因の1つが、「アンダーマイニング効果」です。
アンダーマイニング効果を防ぎ、逆にやる気やモチベーションを高める「エンハンシング効果」を引き出すには、人材マネジメントにおける工夫が必要です。
本記事ではアンダーマイニング効果の意味や定義、発生する原因、具体的な影響などについて解説します。
アンダーマイニング効果とは?
アンダーマイニング効果(Undermining Effect)とは、金銭やご褒美などの物質的な報酬を与えた結果、かえって相手のやる気やモチベーションを削いでしまう現象を意味します。
心理学の用語で「抑制効果」「過正当化効果」といいます。
これまではやりがいや好奇心といった内発的動機づけを原動力としていたのに、金銭やご褒美といった外発的動機づけを与えてしまうことで、報酬が行動の目的になってしまうことがあります。
このように、内発的動機づけに基づく行動に外発的動機づけを行うことで、報酬なしではやる気になれずモチベーション低下に繋がってしまいます。
アンダーマイニング効果が起こる原因
アンダーマイニング現象はなぜ起こるのでしょうか。アンダーマイニング効果を引き起こす3つの理由について見ていきましょう。
行動目的が「やりがい」ではなく「報酬」に変わる
「目標を達成したい」「人のための役に立ちたい」といった内発的な動機付けによって、本人がやる気やモチベーションを感じているケースが多いです。やる気のある行動が業績に繋がっていれば、昇給やボーナスなどの金銭的報酬を与えて、さらにやる気やモチベーションを引き出そうと考えるかもしれません。
しかし、お金や物の物理的な報酬を渡されると、人間はどうしてもその喜びを求めるようになります。 内発的動機付けが無意識のうちに外発的動機付けにすり替わり、やりがいや世のため人のために自ら行っていた行動が、いつのまにか金品やボーナス目当ての行動になってしまうからです。
今までは報酬がなくても充実していた仕事が、急に味気なく感じられ、金銭的な報酬なしではやる気がでなくなってしまいます。
ノルマや締め切りがある
設定目標を達成するため、ノルマや締切などを設けることも多いですが、このような外発的動機づけは一時的なモチベーション向上に過ぎず長続きしません。
外発的動機づけには金銭などの褒賞だけではなく、強制力や罰則も含まれるため、注意が必要です。
自己肯定感が低下し「やらされている」と感じる
内発的動機が目的の場合は、自発的に行動できます。
しかし外発的動機づけが目的になってしまうと、人にやらされている感覚を覚え始めます。 自己決定感や有能感が著しく低下した結果、自分の内面から生じる欲求が叶わなくなり、次第にやる気が失われてしまうのです。
マネジメント能力やリーダーシップを高めるためにも、アンダーマイニング現象の理解は必要不可欠です。
人間に備わった2種類のモチベーションとエンハンシング効果との違いは?
アンダーマイニング効果についての理解を深めるため、人を動かす2種類のモチベーションについて知っておきましょう。
外発的動機づけ
物質的な報酬を与えたり、罰則を与えたり、外的な要因から生まれる受動的なモチベーションを「外発的動機づけ」といいます。
外発的動機づけには、次のようなものがあります。
・罰金を避けるため、無遅刻無欠席を継続しよう
・ボーナスアップのため、前月よりも営業成績を改善しよう
・上司の評価を上げるため、もっと熱心に仕事へ取り組もう
内発的動機づけ
外的な要因によらず、自分の内側から自然と沸き起こるモチベーションを「内発的動機づけ」と呼びます。
内発的動機づけの具体例は次の通りです。
・仕事にやりがいを感じるから、もっと頑張りたい
・もっと自分のスキルを高め、営業成績を向上させたい
・来月から仕事の姿勢を変えて、上司に認めてもらいたい
こうした内発的動機づけがある状態にもかかわらず、外発的動機づけを行ってしまうのが、アンダーマイニング現象が起きる主な原因です。
エンハンシング効果との違いは?やる気を生み出す心理効果
アンダーマイニング効果とは対照的に、人のやる気やモチベーションを高める心理効果のことを「エンハンシング効果(Enhancing Effect)」といいます。
エンハンシング効果とは、外発的動機づけにより、本人の姿勢や考え方を変化させ、内発的動機づけを生み出すことを意味します。
人材のマネジメントや、リーダーシップを発揮するうえで、アンダーマイニング効果ではなく、エンハンシング効果を引き出すよう心がける必要があります。エンハンシング効果によって、従業員がやりがいを持って活躍できる組織づくりを目指せます。
エンハンシング効果について詳しくはこちらの記事をご覧ください。
エンハンシング効果とは【モチベーション/組織づくり】
アンダーマイニング効果を実証した実験
・ソマパズルを用いた実験
1971年、心理学者のデシ氏とレッパー氏が当時流行していたソマパズルを用いて、大学生を2つのグループに分け、3つのセッションで実験を行いました。
セッション1:それぞれのグループにパズルを解いてもらう。
セッション2 :1グループにはパズルが解けたら報酬を与え、もう1グループには何も告げず、報酬も与えない。
セッション3:それぞれのグループにパズルを解いてもらう。報酬はどちらにも与えない。
何の報酬も与えていなかったグループは、ソマパズルに触れる時間の変化は見られず、報酬を与え得られたグループのみ、ソマパズルに触れる時間が減少しました。
金銭的な報酬を与えられたことで「ソマパズルは報酬を得るための手段にすぎない」と感じるようになったのです。
この実験の結果、内発的な動機が失われてパズルへのモチベーションが低下したことがわかりました。
・幼稚園児を対象にしたお絵描きの実験
幼稚園児を対象にしたお絵描きの実験でもこの結果は同様でした。
絵を描くことが好きな園児を以下3つのグループに分け、しばらくたった後に内発的なお絵描きがどのくらい行われているかを測定した実験です。
Aグループ:上手に描けたら賞状をあげる、と伝えて実際に賞状を与える
Bグループ:賞状をあげることは伝えないが、描き終えたら賞状を与える
Cグループ:約束もせず賞状も与えない
この実験においてもB、Cグループの園児たちに内発的な意欲の低下は見られず、Aグループの園児だけに意欲の低下が見られました。
ビジネスシーンにおけるアンダーマイニング効果の影響
生産性が低下し、離職率が高まる
退職者の中には、モチベーションを高く維持したまま次のステージを選んで退職する人もいますが、多くの場合はモチベーションの低下とともに退職を考えます。
内発的動機づけを増やしアンダーマイニング効果を抑えれば、離職率の低下に繋がるでしょう。
やりたくないことや辛いことに対して集中力や関心が削がれるのは、人として当然の現象です。
アンダーマイニング効果は企業の生産性に大きく影響します。
職場の人間関係が悪化し、再びモチベーションを上げるのが困難になる
報酬制度は従業員の競争意欲を高めると同時に競争を促すものです。
競争自体はモチベーションや成長意欲を生むため悪いことではありません。
しかしこれに報酬が絡んでくると「報酬が得られる人の利益になるような行動は、自分にとって不利益をもたらすので控えよう」といった考えが生まれてくるのです。
一度アンダーマイニング効果が起きてしまうと、そこから再びモチベーションを上げるのは困難です。
アンダーマイニング効果を防ぐ4つの対策
アンダーマイニング効果は、誰にでも起こり得る現象です。
この現象が起きるのを防ぐためにはどうすれば良いのでしょうか。次の4つのポイントを心がけましょう。
相手のモチベーションの種類を見極める
アンダーマイニング現象は、すでに十分な内発的動機づけがあるにもかかわらず、余分な外発的動機づけを行うことで発生します。
従業員のやる気やモチベーションを評価し、内発的動機づけ、外発的動機づけのどちらに基づいて行動しているかどうか、あらかじめ見極めることが大切です。
すでに十分な内発的動機づけがある場合は、無理に物質的な報酬を与えるよりも、声掛けやコミュニケーションによる「言語的な報酬」を与えましょう。
期待の言葉や褒め言葉は、本人の有能感や自己決定感を損ないにくく、相手のやる気やモチベーションを高めるエンハンシング効果や、心理的な思い込みによりパフォーマンスを向上させる「ピグマリオン効果(Pygmalion Effect)」も期待できます。
正しい「褒め方」が内発的動機づけにつながる
部下や後輩を褒める際は、正しい「褒め方」を実践しましょう。
心理学の研究では、相手を褒める際は「結果・能力」ではなく、「過程・姿勢」を褒めることで、内発的動機づけにつながることが示されています。
従業員の結果・能力を褒めると、これ以上の結果が出ないことへの恐れや自分の能力への慢心が生じ、かえってやる気やモチベーションが損なわれるケースがあります。
一方、従業員の業務プロセスや仕事への取り組み方を褒めることで、成果や業績にかかわらず、さらなる努力を引き出すことが可能です。
アンダーマイニング効果ではなく、エンハンシング効果を引き出すため、「褒め方」にも気を配りましょう。
「強いられている」と感じさせない
・人は外発的動機付けによって「他者にコントロールされている」と感じる
アンダーマイニング効果を防ぐための方法として挙げられるのが「他人から強いられていると感じさせないこと」です。
人は生まれながらにして、好奇心や探求心を持ち活動的であるとされており、他人から強要されている状況を嫌う傾向にあります。
つまり「自分がやりたいと思うことだからやっている」という意欲を持続させるのが重要なのです。
モチベーション向上のため、よかれと思って与えた金銭的報酬が結果として内発的動機づけを下げる場合もあります。
金銭的報酬によって、もともと自発的に行っていた行動が「報酬のためにやらされている行動」になってしまうのです。
なかには報酬によって意欲的に取り組む社員もいるでしょう。
それと同時に、自主性や積極性が低下する社員もいる点を覚えておかなければなりません。
・従業員の自己決定感を保つためにも、言動に気を付けて「強いられて働いている」と感じさせないことが大切
従業員の内発的動機づけを強め、モチベーションや生産性のアップにつなげたい場合は、物質的な報酬ばかりでなく言語的な報酬が有効です。
信頼している上司やチームスタッフから言語的なフィードバックや賞賛を得られれば、アンダーマイニング効果の発生を防げます。
やる気のない従業員に対しては、まず成績が伸びたらボーナスを支給する、というような外発的動機付けは非常に有効な手法です。
しかし、反対にやる気のある従業員に対しては、期待や、賞賛の言葉といった言語的な報酬を与えるほうが、自己決定感や有能感を低下させず、内発的な意欲を向上できます。
簡単な目標を設定してみる
業務を正確に進めてもらうためには、行動計画や簡単な目標など、細かく設定することも大切です。しかし、あまりにも細かく設定してしまうと、従業員にとってはどうしても「強いられている」と感じてしまい、自己決定感やモチベーションの低下を引き起こす可能性があります。細かな判断は従業員本人に任せてみましょう。
実力や経験不足のメンバーに対しては、簡単な目標を自分の力で乗り越えられたという経験を繰り返すことで、達成感が自信につながり、内発的動機づけを強める効果が期待できます。
従業員それぞれのスキルや実力に応じた目標設定をしてみましょう。
アンダーマイニング効果を防いでやる気やモチベーションを引き出す工夫を
金品やボーナスを始めとした物質的報酬を与えた結果、かえって従業員のやる気やモチベーションが削がれてしまう現象を「アンダーマイニング効果」と呼びます。
アンダーマイニング現象を防ぎ、従業員のやる気を引き出すには、「内発的動機づけ」「外発的動機づけ」のどちらに基づいて行動しているかの見極めが大切です。
また、部下や後輩を褒める際は、「褒め方」にも注意しましょう。
人材活用に課題を感じている経営者の方には、成果を出す方法を体系的に学べる武蔵野の経営計画書がおすすめです。
経営計画書とは、会社の数字・方針・スケジュールをまとめた手帳型のルールブックです。
750社以上の企業を指導する株式会社武蔵野 代表取締役社長 小山昇の経営哲学が詰まった
経営計画書の作成手順・作成フォーマットの内容となっています!
ぜひ、こちらからダウンロードしてください。



 ポストする
ポストする シェアする
シェアする LINE
LINE この記事は約4分で読めます。
この記事は約4分で読めます。