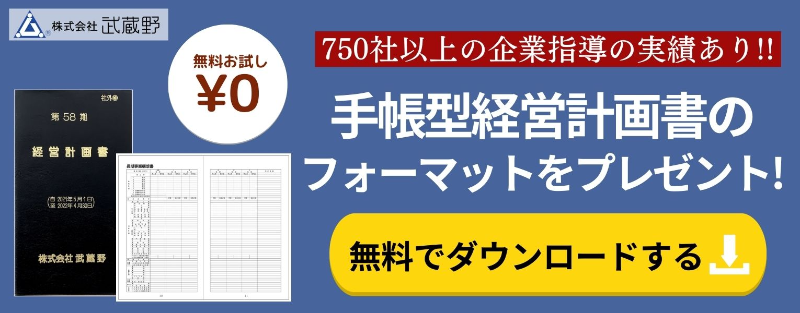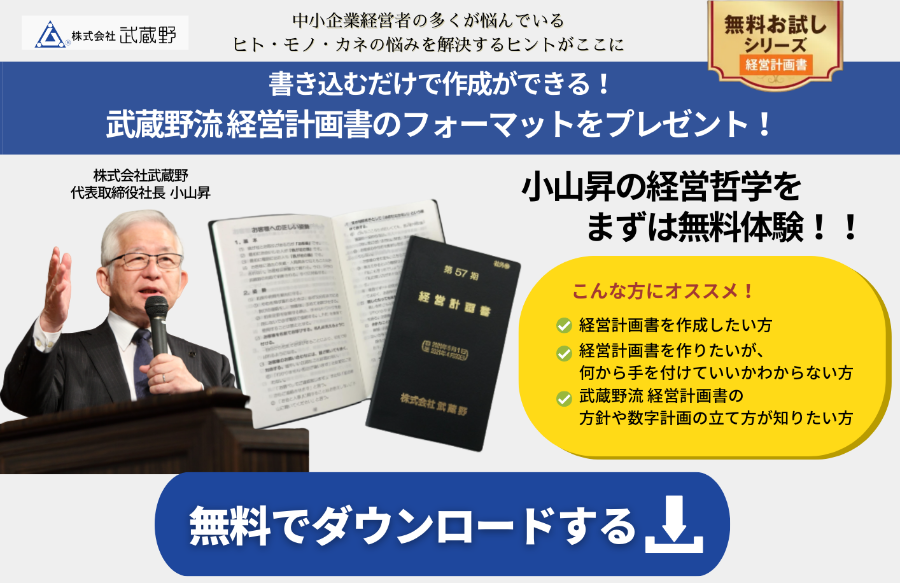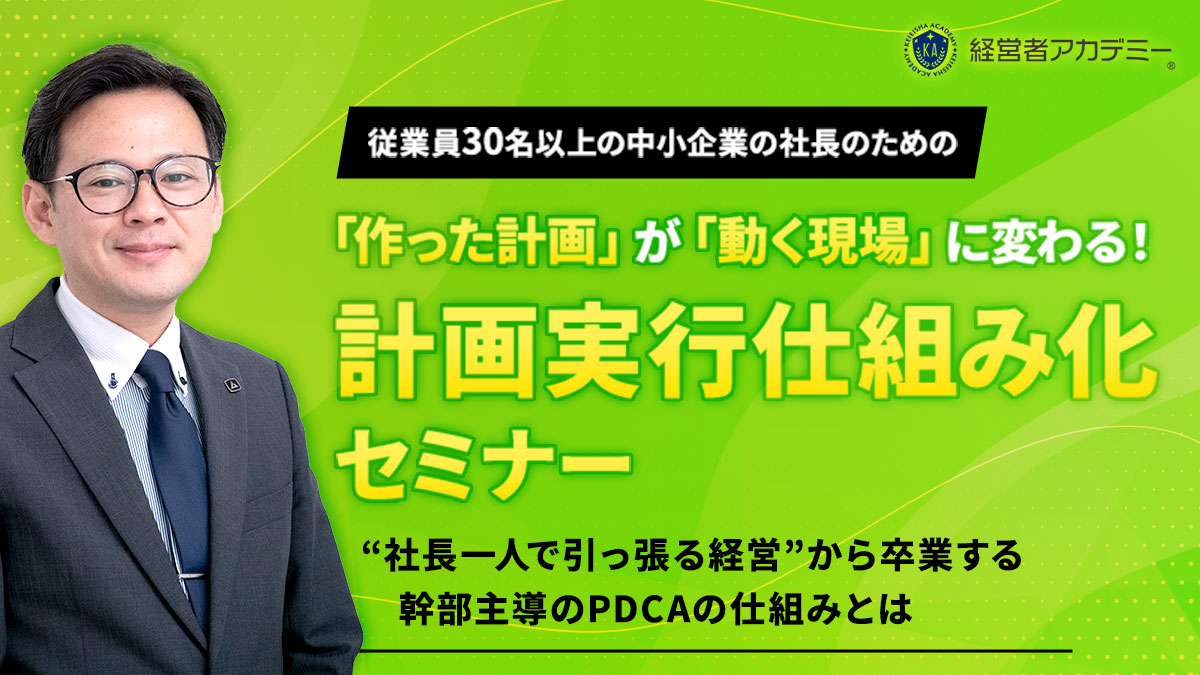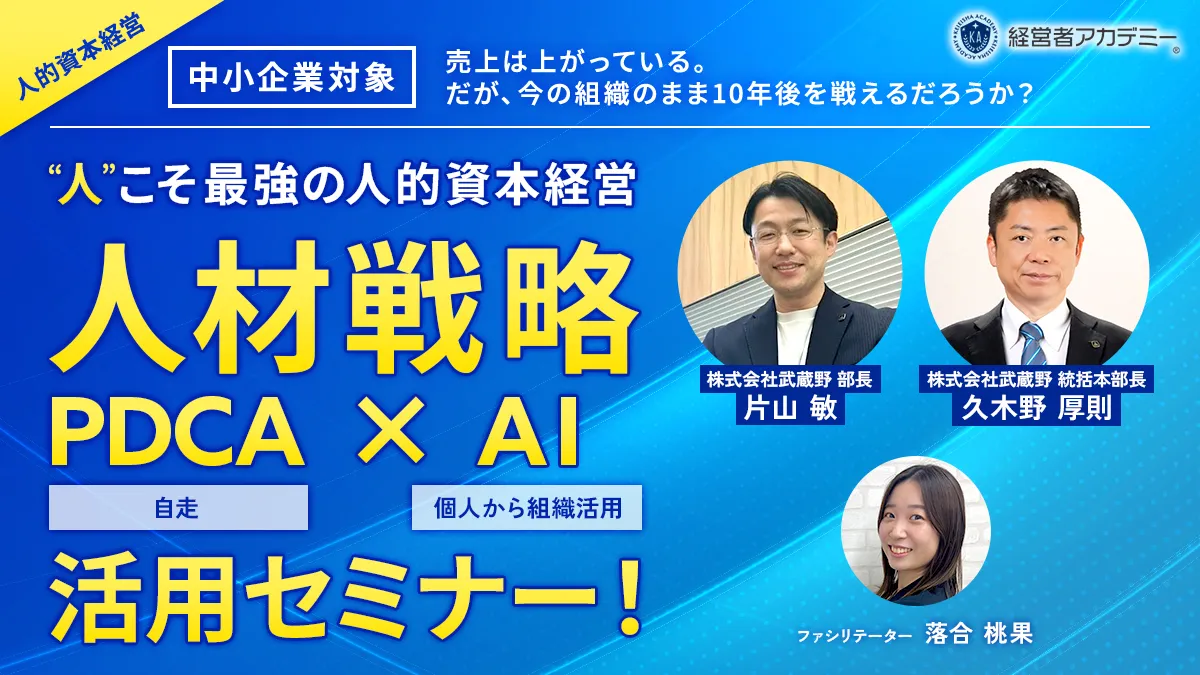集団における共通のミッションを達成するためには、「グループダイナミクス」の考えが重要となります。
グループダイナミクスとは、ドイツの心理学者であるクルト・レヴィン氏によって研究された集団力学のことです。
本記事では、グループダイナミクスについて、集団擬似性やグループシンクを解説します。
グループダイナミクスの基礎概要と課題を深く理解できるでしょう。
グループダイナミクスとは?
グループダイナミクスとは、集団における個人の行動や思考は集団から影響を受け、その個人の考えは集団に対して影響を与えるという集団特性を示します。
このグループダイナミクスは、社会心理学の一分野として研究されており、
特に個人行動の集合体として捉えられない集団的行動の発生源がテーマとして扱われることが多いです。
具体的には下記のような内容があげられます。
- どのような条件や状況下において集団の擬似性が高まるのか
- どのようなリーダーに対して、どのようなメンバーが協力的・積極的になるのか
- どのようなビジョンをどう設定すれば、集団を構成する各個人が互いに協力してそのビジョンに向って行動するのか
なお、グループダイナミクスはビジネスにおいても有効活用されています。
例えば、トレーナーがグループダイナミクスを活用して場を活性化させ、受講者に対して気づきや意欲を高めるなどの効果が見込めます。
グループダイナミクスに影響を与える集団擬似性
グループダイナミクスには、集団擬似性(集団の団結力)の影響があり、集団擬似性が高まるほど集団圧力の大きさが増します。
なお、企業においての集団擬似性は下記の要素で形成されています。
- 共通のミッションがあるのか
- 共通のビジョンがあるのか
- 共通のバリューを持っているのか
- 集団が小規模であるのか
- メンバーの入れ替わりが少ないのか
- 経験を共有している時間の長さはどれくらいか
グループダイナミクスを活用するためには、企業や組織で集団擬似性の要素を深く考え、各個人がお互いに協力して計画を進める必要があります。
それだけでなく、メンバーに適合するようなチームリーダーを選定し、メンバー全員が協力的になるようなチーム編成にしなければなりません。
グループダイナミクスのメリット
グループダイナミクスを活用することでどのようなメリットがあるのかご説明します。
チームスキルの向上
グループダイナミクスの大きなメリットは、自身の持つスキルより高いレベルのグループに属することで、より高いパフォーマンスを手に入れることができます。
メンバー同士が支え合い、相乗効果でメンバー間の協力や連帯感を醸成し、チームワークを向上させることができます。
チームのリーダーにレベルの高い人材を起用することで、全く違うレベルの高いチームに変貌する場合があるのもグループダイナミクスのメリットです。
相互理解とコミュニケーション
グループダイナミクスでは、メンバー間でのディスカッションやディベートを通して様々な観点から意見を交わすことで、自分が気付かない側面に気付くことができます。
そのため、多くの企業が人事評価や社員育成にグループダイナミクスを役立てています。
自分ではあまり気にしていないことを他の多数が気にかけていることなども明らかになるので、個人の評価に大いに役立ちます。
メンバー同士が相互理解を深めることで、コミュニケーションスキルを向上させることができます。
グループダイナミクスとグループシンクの関係性
グループシンク(集団浅慮)とは、合意に至ろうとするプレッシャーにより、集団における多様な視点からの評価が欠落する状態のことを意味します。
グループダイナミクスは集団擬似性の強さに影響を受けると同時に、支配的なリーダーによってグループシンクが発生しやすくなります。
集団がグループシンクに陥ると意思決定が極端となり、共通のミッションを達成できなくなります。
なお、このグループシンクの原因は集団による責任分散であるため、各個人が冷静に物事を考え、多様な選択肢を検討していかなければなりません。
そのためグループダイナミクスを活用する際には、集団がグループシンクに陥らないよう注意することが大切です。
グループシンクに起因するグループシフトの種類
グループシンクに起因する極端な意思決定のことをグループシフトといいます。
グループシフトには「リスキーシフト」と「コーシャスシフト」といった種類が2種類あります。
リスキーシフト
一人だと慎重かつ理性的な行動を取れる人間が、グループシンク(集団浅慮)によって、
よりリスクの高い意思決定に加担してしまう現象を指します。
集団により責任が分散されることによる意識の欠如と言われており、
「赤信号、みんなで渡れば怖くない」という言葉がまさにリスキーシフトを的確に表現しています。
コーシャスシフト
リスキーシフトとは相反する現象で、一人だと大胆な行動を取れる人間が、
グループシンク(集団浅慮)によって、より慎重な方向の意思決定に加担してしまう現象を指しています。
集団を形成する各個人の安全志向が強い場合に生じやすくなる現象です。
本当のグループダイナミクスについて
ここまでグループダイナミクスについて解説しましたが、本当の意味でこのグループダイナミクスを理解している方は多くありません。
そこで、本項では本当のグループダイナミクスについてお話します。
人間は社会的な動物であることから、常に社会や他者との関わりを持ちながら生活しています。
それらの関わりによってその人にどのような「変化」をもたらすか、それが本当のグループダイナミクスです。
グループダイナミクスを活用する際の注意点
集団疑似性が高まるとグループのコミュニケーションは活発化する
集団疑似性が高いほどグループのコミュニケーションは活発になります。
また、グループの意見から逸脱している人に対しても、積極的なコミュニケーションを図ろうと行動するため組織は活性化していきます。
しかし逸脱者に変化が見られない場合、時間と共にコミュニケーションは減少し、最終的には阻害する傾向があるので注意が必要です。
集団の結束力が高まるほど排他的になり、他グループとの対立や軋轢が生じる
集団疑似性(集団の団結力)が強い場合、他の集団に対し排他的になる傾向があることから、
相反する意見や態度、要求などが存在し、互いに譲らない緊張状態(コンフリクト)が生じやすくなります。
しかしコンフリクトは、必ずしもマイナスであるとは言えません。
互いに議論し、考え、意見交換することで相手への理解が深まるほか、
対立によって競争力を高めて新しいアイデアを生み出すなど、ポジティブな力に変えることが大切です。
グループダイナミクスと心理的安全性の関係
「心理的安全性」という言葉を最近よく耳にするかと思います。
心理的安全性とは、他社からの反応に怯えたり羞恥心を感じたりすることなく、自身をさらけ出すことができる状態を意味します。
会社においては、社員が安心して仕事に打ち込める環境のことを指します。
実は、グループダイナミクスと心理的安全性には相関性があると言われています。
グループダイナミクスは、集団における社員行動について研究した理論で、集団力学のプレッシャーがどのような条件で働くのかを示しています。
それに対し心理的安全性は、どのようにすれば社員が仕事に安心して打ち込めるのかを示しています。
つまり心理的安全性の高い組織であれば、グループダイナミクスの考え方を活用し、職場がどうすれば働きやすい環境になるのかを考えることができます。
心理的安全性について詳しく知りたい方は下記より無料の資料をご覧ください。
心理的安全性の高い組織・職場の作り方
グループダイナミクスを活用して場を活性化させよう
ここまで、グループダイナミクスについて、集団擬似性やグループシンクを解説しました。
グループダイナミクスは、ドイツの心理学者である「クルト・レヴィン」によって研究された集団力学を指します。
ビジネスシーンでは場を活性化させるため、このグループダイナミクスを活用するケースがあります。
また、グループダイナミクスは集団擬似性の影響を多分に受けると同時に、グループシンクの課題にも注目しなければなりません。
安全に活用するためにも本記事を参考にし、本当のグループダイナミクスで場を活性化させましょう。
株式会社武蔵野は「経営計画書」による経営や社員教育を行うことで、社員の心理的安全性を高めています。
経営計画書とは、会社の数字・方針・スケジュールをまとめた手帳型のルールブックです。
750社以上の企業を指導する株式会社武蔵野 代表取締役社長 小山昇の経営哲学が詰まった
経営計画書の作成手順・作成フォーマットがセットになった無料資料をプレゼントしていますので、ぜひこちらからダウンロードしてください。



 ポストする
ポストする シェアする
シェアする LINE
LINE この記事は約2分で読めます。
この記事は約2分で読めます。