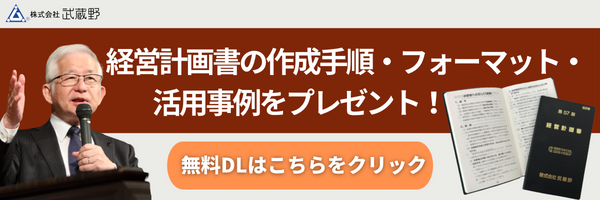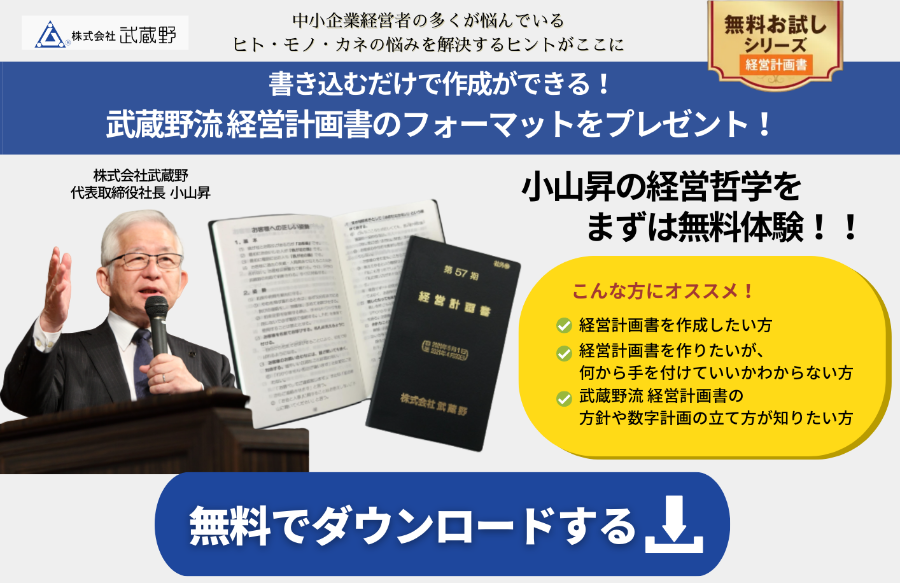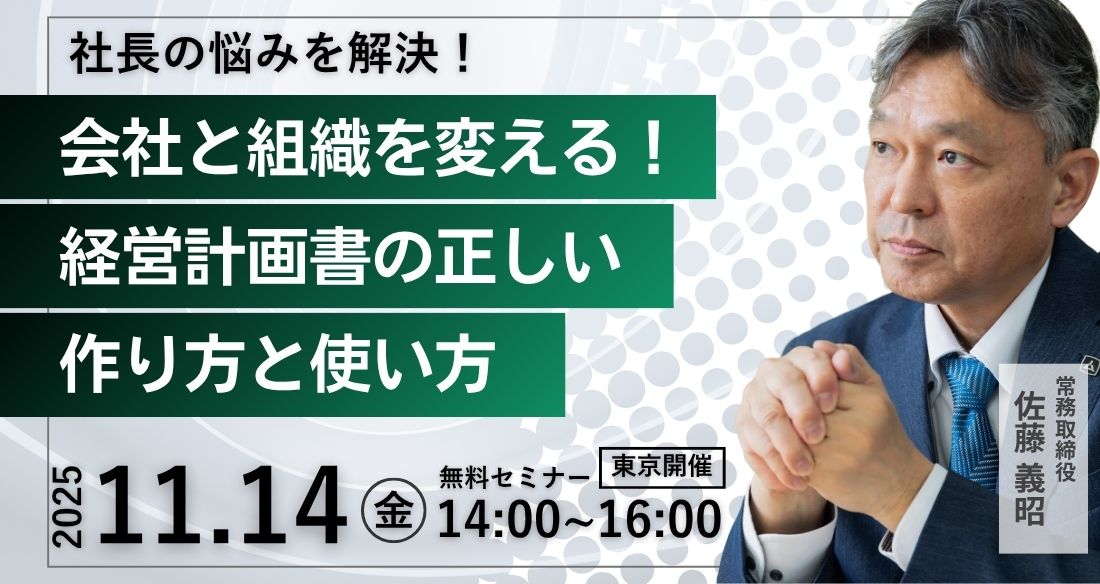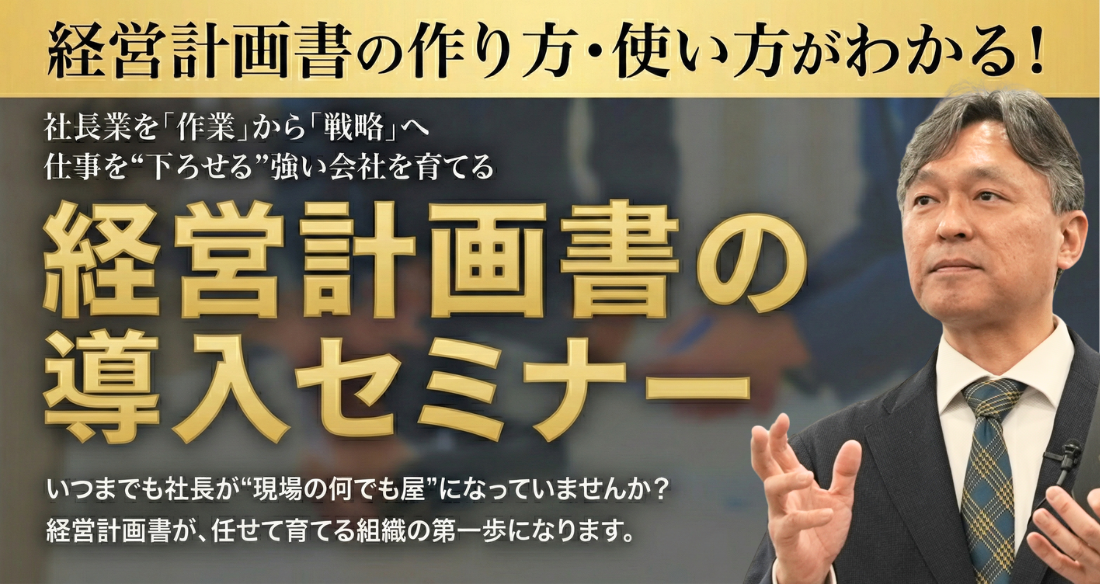エン・ジャパンの調べによると、会社に属しながら仕事がない「社内失業者」がいる企業は、予備軍もふくめて約29%に達しています。[注1]
他の社員と同じ給料を受け取りながら、仕事をサボる・怠ける社員のことを「フリーライダー社員」と呼びます。
フリーライダー社員は周囲に悪影響を与え、放置しているとどんどん増殖していくため、早急にフリーライダー社員対策に取り組むことが大切です。
この記事では、フリーライダー社員の特徴や基本知識、社員のフリーライダー化を防ぐ3つの人事施策について、わかりやすく解説していきます。
[注1] エン・ジャパン株式会社:300社に聞く「社内失業」実態調査―『人事のミカタ』アンケート―
フリーライダー社員とは?「タダ乗り社員」は放置するとどんどん増える
「フリーライダー(Free Rider)」とは、本来集団の利益にタダ乗りすることを意味し、対価を払わずに公共財を利用することを指す言葉ですが、ビジネスシーンでの意味合いは少々異なります。
ビジネスシーンでのフリーライダーとは、他の社員と同等の報酬を受けとっているにもかかわらず、自分は仕事をせずに怠け、他人に責任を押し付けてばかりいる社員のことです。
会社や社会に貢献する以上の利益を得ており、他人の評価を自分のものにすることで、事業活動に活用されていない人材のため、その存在が問題視されているのです。
フリーライダー社員には次の5つの特徴があります。
- 仕事をまったくしないか、仕事に時間がかかっている
- 他人の仕事にタダ乗りし、成果を横取りしている
- 攻撃的な言動が多く、他人のモチベーションを下げている
- 仕事への責任感が乏しく、ミスをしても責任転嫁ばかりする
- 周囲の人間に負担をかけ、チーム全体の生産性を下げている
「フリーライダー社員」とよく似た概念として、「ローパフォーマー」があります。
ローパフォーマーとは、純粋な業務遂行能力が低く、期待よりも低い成果しか出せない社員のことを意味します。
フリーライダー社員はローパフォーマーと違い、そもそも仕事への意欲が乏しい場合がほとんどです。
そのため、勤務態度を改善することで、一定のパフォーマンスを発揮できるケースもあります。
フリーライダー社員はなぜ増えるのか。原因と対策とは
フリーライダー社員はなぜ生まれてしまうのでしょうか。
フリーライダーが発生する主な原因は、終身雇用制度や年功序列の評価制度、余剰人員などによるものです。
自身の役割を果たさなくても報酬をもらえる場合に、段々とやる気がなくなり、それがフリーライダー誕生の原因となっています。
フリーライダーは自分の任務を完遂しようといった考えがなく、手抜きや不手際といった自分の問題でチームや会社に迷惑をかけても、周囲に対して申し訳ないといった気持ちにならないのです。
フリーライダー社員を放置していると、意欲・やる気のなさが周囲に伝播し、フリーライダー社員がどんどん再生産されてしまいます。
そのため、フリーライダー社員が生まれないような職場環境づくりや、フリーライダー社員を早期発見できる評価制度づくりが大切です。
フリーライダー社員が増殖すると、組織力が大きく低下し、企業の成長の妨げになります。
フリーライダー社員を放置せず、常に社員1人ひとりの仕事内容や勤務態度に目を配ることが大切です。
フリーライダー社員を減らす3つの対策
フリーライダー社員を減らすため、次の3つの対策を導入しましょう。
1人ひとりの仕事内容を「見える化」する
フリーライダー社員に怠けさせない、仕事をしているふりをさせないため、1人ひとりの仕事内容を「見える化」する仕組みをつくることが大切です。
簡単な例では、1人ひとりの社員に作業日報を書いてもらい、業務内容をチェックする方法があります。
また、ホワイトボードなどに1人ひとりのタスクカードを貼っていく「かんばん方式のタスク管理」も、従業員全員の仕事内容を視覚化でき、フリーライダー社員の「サボり」を防止します。
定期的に面談を実施し、フリーライダー化の芽を摘む
フリーライダー社員がやる気を失っているのは、何か仕事に対する不安や悩みがあるからかもしれません。
上長と社員が1on1でミーティングを行う機会を設けることで、仕事の不安や悩みを取り除き、社員のフリーライダー化の芽を摘むことが可能です。
また、上長が定期的に面談を実施することで、日々の仕事に適度な緊張感が生まれ、怠けにくい・サボりにくい組織風土をつくることができます。
仕事への取り組み方も積極的に評価する
人事評価制度を改革し、仕事の成果だけでなく取り組み方も評価項目へ盛り込むのも効果的です。
「勤務態度も人事評価に影響する」「頑張って仕事に取り組めば、きちんと評価してくれる」という意識が社員に浸透することで、仕事へのモチベーションを取り戻すきっかけをつくり、社員のフリーライダー化を防ぎます。
業務プロセスに着目した人事評価制度の例として、上長だけでなく周囲の同僚などの評価も参考にする「360度評価」や、従業員同士が仕事への取り組み方に応じてお互いに報酬を贈り合う「ピアボーナス」などが挙げられます。
フリーライダー社員を減らすため、組織風土改革や人事制度改革に取り組みましょう。
フリーライダー社員を減らすことが業績アップのポイント
業績アップのポイントは、仕事をサボる・怠ける「フリーライダー社員」を減らすことです。
フリーライダー社員は周囲に悪影響をもたらすため、フリーライダーを放置すると、さらに周囲の社員がフリーライダー化するという悪循環が生まれます。
チームにフリーライダーがいると、優秀な社員が離職する可能性も高くなります。
ストレスが溜まったり、仕事にやりがいを感じられなくなったりすることで、組織に所属する意味を見失ってしまい、その結果、離職や転職を考えるきっかけとなり、組織から優秀な社員が去ってしまうことになります。
そのようなことを防ぐためにも、毎日の業務に適度な緊張感が感じられるような職場環境をつくりましょう。
さまざまな職務の責任の範囲や所在を明らかにすることで、誰が責任を負うのかを明確に定義します。
そうすることで、一人ひとりが背負う役割の曖昧さを排除し、社員に責任感をもたせることが可能となり、フリーライダー社員を減らすことができます。
フリーライダー社員は「ローパフォーマー」だとは限りません。
意識改革の結果、会社組織に大きく貢献する「ハイパフォーマー」に化ける可能性もあるため、あきらめず組織風土改革や人事制度改革に取り組むことが大切です。
人材活用や経営計画について課題を感じている経営者の方には、成果を出す方法を体系的に学べる武蔵野の無料ダウンロードコンテンツがおすすめです。
750社以上の企業を指導する株式会社武蔵野 代表取締役社長 小山昇の経営哲学が詰まった
経営計画書の作成手順・作成フォーマットがセットになった充実の内容となっています!
ぜひ、こちらからダウンロードしてください。



 ポストする
ポストする シェアする
シェアする LINE
LINE この記事は約2分で読めます。
この記事は約2分で読めます。