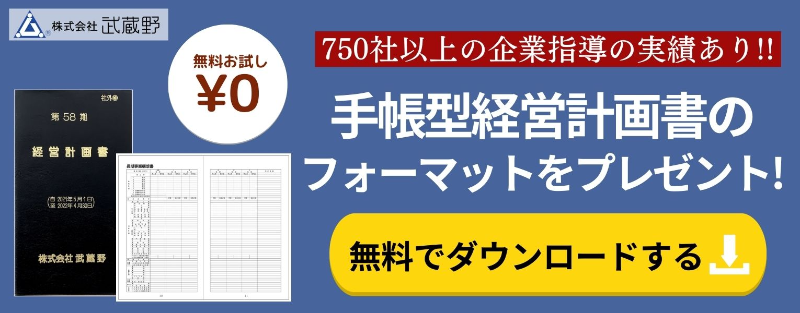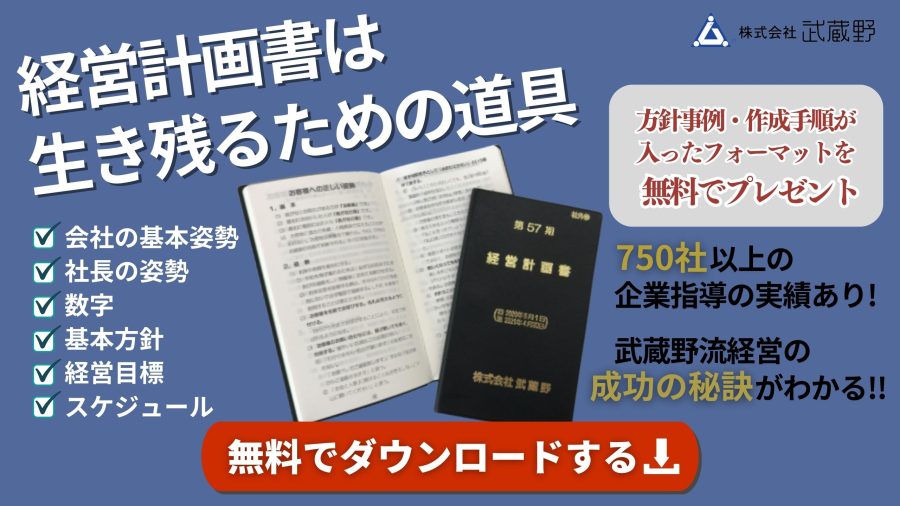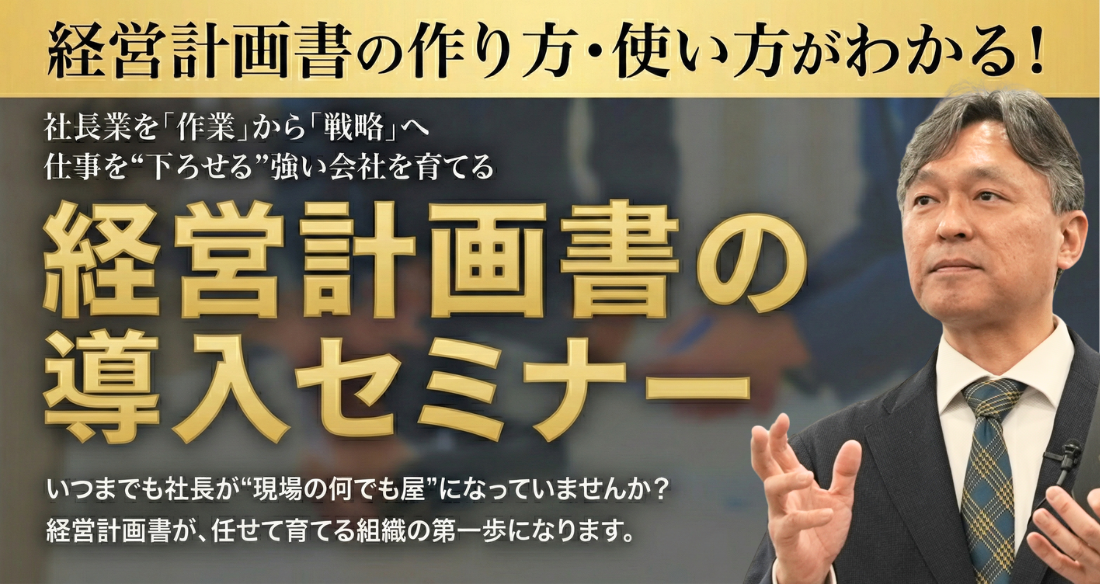「能力はあるのにやる気がなくてもったいないな…」このような状態に陥っている社員が周りにいるという方もいらっしゃるのではないでしょうか。
リモートワークが普及してきた現在、多くの企業で個人の生産性の向上が課題となっており、ぶら下がり社員が問題視されています。
周囲から期待されて入社した社員が、一体なぜぶら下がり社員になってしまうのでしょうか。
本記事では、ぶら下がり社員が生まれる背景や、対策方法などについてご紹介します。
ぶら下がり社員とは
ぶら下がり社員とは、仕事へのモチベーションが著しく低く、上司から指示されたことだけを淡々とこなし、求められる以上の役割は決して行うことがない社員のこと。
昇進意欲がなく、文字通り会社にぶら下がっている社員です。
「退職はしない、でも頑張らない」のスタンスでいるぶら下がり社員は、常に受け身ですが、与えられた仕事はこなすため、フリーライダーやローパフォーマーといった重大ミスを連発する社員と異なり、会社に対して直接的な損害を与えるわけではありません。
フリーライダーについて詳しくはこちらの記事をご参照下さい。
フリーライダー社員とは?企業におけるフリーライダー社員対策を紹介
しかし、働き方改革の推進や新型コロナウイルスの影響で、人材の活用や生産性の向上がより一層求められるようになった現在、ぶら下がり社員の存在も見過ごすことができない問題です。
ぶら下がり社員の特徴
ぶら下がり社員の特徴としては、言われたことしかやらず居心地の良さに甘えている、組織や自分自身の能力を諦め仕事全体に消極的、自信がなく出世意欲がない、などが挙げられます。
仕事への目的意識や成長意欲はなく、現状の環境に満足していることが多いため、管理職になって部下を持つことを嫌がる傾向があります。
年代としては、20代後半~40代にかけて多くなっています。
では、なぜこのようなぶら下がり社員が生まれてしまうのでしょうか。
ぶら下がり社員が生まれる背景
ぶら下がり社員になってしまう人材は、自分や会社に対してネガティブな感情を抱いていることが多いとされています。
ぶら下がり社員が生まれる背景にはどのようなことがあるのでしょうか。
居心地の良さ
ある程度規模が大きい企業の場合、仕事で成果を出さなくても毎月決められた給与は支払われます。
このような環境においては、元々仕事への意欲が低いぶら下がり社員は、指示されたこと以上の仕事をこなそうとはしません。
人員に変化のない組織体制や、社員の声を聞いて改善を行わない組織では、従業員は次第にやる気を失っていきます。
従業員アンケートなどで、意見を収集・改善できる仕組みを作り、定期的なジョブローテーションの検討なども有効的でしょう。
自分に自信がない
ぶら下がり社員になる人の多くは、自分に自信がない傾向があります。
「たとえ結果を出したとしても評価してくれる人はいるのだろうか」「自分が頑張ったところでチームのプラスにはならない」
というネガティブな思考から、上司から与えられたタスクをこなすだけになってしまうのです。
自分が傷つきたくないという自己防衛だったのが、次第に習慣化されてしまい、仕事の目的を見失っている状態であるといえます。
ぶら下がり社員が増えると起こるデメリット
ぶら下がり社員が社内に増えると起こるデメリットは、「管理職が増えない」「消極的な組織風土になる」の2つです。
これにより、企業の成長が停滞する可能性が高まります。
ぶら下がり社員の割合が多いといわれている30代~40代のミドル層は、中間管理職に昇進するチャンスがあります。
しかし、管理職になることを嫌がるぶら下がり社員が増えると、管理職を担う人材が育たず、企業全体が弱体化することに繋がります。
若手を指導する存在もいないため人材育成が進まず、さらには若手層の登用を行うのが難しくなります。
また、マイナスな雰囲気は組織に伝染しやすく、周りに悪影響を及ぼす可能性があります。
組織にぶら下がり社員が一人でもいる場合、それを見ている他の人も「あの働き方でも給与が貰えるなら、自分も頑張る必要はないか」という考えになり、組織全体がやる気を失うことがあります。
ぶら下がり社員が増えやすい組織の特徴
ぶら下がり社員が増えやすい組織の特徴として、3つ解説します。
キャリアパスが明確でない
キャリアパスが明確ではない組織は、自身の将来について考える機会が少なくなり、将来への漠然とした不安に繋がっていきます。先行きに希望や可能性がなくなることで意欲的に挑戦できなくなり、守りの姿勢に入ってしまうのです。
変化がない
変化が少ない組織では、組織内に刺激や緊張感がなくなることで、気持ちが緩みがちになり、ぶら下がり社員の多い組織となっていきます。また変化を拒んでばかりの組織では、従業員は何をいっても無駄といったような感情が強くなり、次第にやる気を失っていきます。
仕事を分業化しすぎている
分業して仕事を進めるやり方は、組織として効率をあげる手段となりますが、分業化を過度に進めてしまうと、ぶら下がり社員を生む一因にもなり得ます。同じような作業をひたすら繰り返すだけということが多くなり、仕事に対するやりがいを見失ってしまい、ぶら下がり社員になりやすくなってしまいます。
ぶら下がり社員への対処方法
ぶら下がり社員を放置していると、本人の能力を生かしきれないだけでなく、組織全体にも悪影響を及ぼしてしまいます。
有能な社員たちをぶら下がり社員にしないために、企業はどのような対策を行う必要があるのでしょうか。
人事評価制度を改善する
人事評価制度を見直し、適切な評価を行い、上司がしっかりと日々の仕事へのフィードバックを行う環境を作ることで、給与以外のモチベーションを保つことができます。
最初のうちは小さなことだけであっても、それらを評価されることで「自分でも上司から評価された」と徐々に自信につながっていき、ぶら下がり社員の意識が少しずつ改善されていきます。
上司・部下間で信頼関係を築く
上司や同僚、部下とのつながりを感じられなくなると、疎外感を感じてぶら下がり社員になってしまうことも。
リモートワークの普及によって、顔を合わせてコミュニケーションを取る機会が減っている今だからこそ、部下が成功したときだけではなく、ミスをした際のフィードバックを行うことが大切です。
「自分が上司から言われたらどう思うか」ということを念頭に置きながら、上司・部下間で信頼関係を築くことができるようなコミュニケーションを取りましょう。
業務で活躍できる場をしっかり与える
ぶら下がり社員を減らすためには、業務で活躍できる場を与えることも大切です。
単純な業務だけではなく、組織への貢献度が高い業務や難易度が高い業務を与えることで、全力で仕事に取り組むようになるでしょう。
「しっかりとやりきった」ということが自信につながり、働く動機が生まれ、生産性の向上が期待できます。
多様なキャリアパスを用意する
働き方も多様化し、先行きも見通せない時代に、ついてこられずにやる気を失ってしまう人がたくさん出てしまわないように、サポートしていくことが重要です。
出世する以外のキャリアパスとして、例えば週5日フルタイムではない形での勤務制度など、多様なキャリアパス、キャリアへの向き合い方を構築するのも一つです。自身が会社でどのように成長していくのかを理解し、将来像を描けます。
社内公募制度などを導入する
本人がチャレンジしたいと思った時に、意欲に応えられる環境を整えておくことも大事です。
社内公募制度などの導入により、自分の意思で新しい仕事にチャレンジできる機会があれば、自分の力で新たなキャリアを切り開いていくきっかけにもなります。また、優秀な人材をつなぎ留めておくためにも重要です。
環境や役割に変化を与える
適度なジョブローテーションの実施により、環境や役割の変化を与えることも有効です。ほどよい緊張感が生まれることで、だらけてしまうのを防ぐことができます。
ジョブローテーションを繰り返していく中で、仕事の全体像を見渡せるようにもなり、自分がやっている仕事の意義を理解できるようになるでしょう。
ぶら下がり社員を減らすことを全社の課題として捉えよう
本記事では、ぶら下がり社員についてご紹介しました。
ぶら下がり社員は、遅刻や欠勤をすることなく、淡々と働くため、一見すると従順な社員に見えます。
しかし、リスクを負うことを避ける傾向があるため、組織の成長が止まってしまうといったデメリットも。
ぶら下がり社員を放置しておくと、周りの社員に伝染し、最終的に組織全体のモチベーションが落ち、会社全体に悪影響を及ぼすことになってしまいます。
ぶら下がり社員を全社の課題として捉え、社員のモチベーション向上を目指しましょう。
人材活用について課題を感じている経営者の方には、成果を出す方法を体系的に学べる武蔵野の無料ダウンロードコンテンツがおすすめです。
ぜひ、こちらからダウンロードしてください。



 ポストする
ポストする シェアする
シェアする LINE
LINE この記事は約3分で読めます。
この記事は約3分で読めます。